2018年6月15日 | 虫
コバエが発生する原因とは?コバエの習性を知って対策しよう

気温が徐々に上がり、過ごしやすくなる時期になると、コバエがちらほらみかけるようになります。周辺を飛び回ると気になる存在であり、大量に発生すると料理に混入したり、食品に卵を産みつけたりといった問題が発生します。また、コバエがどのように家屋に入ってきてどのようにして増えるのかも気になる点です。
本記事ではコバエの生態や発生原因を解説し、効果的な対策方法も紹介します。
コバエの生態

コバエという名称は、小さいハエの種類の総称として使われています。
コバエにはさまざまな種類がいますが、一般的に知られているのはショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエの4つのグループです。
コバエの種類と特徴
ショウジョウバエ
| 全長 | 約2~3ミリメートル |
|---|---|
| 体色 | 黄色 |
| 種類数 | 約3000種類 |
| 日本で確認されている種類数 | 約260種 |
ショウジョウバエは、一般家庭で最もよく見かけるコバエの仲間です。ショウジョウバエの代表種であるキイロショウジョウバエは、黄色っぽい体色をしており目が赤いのが特徴です。
熟した果物に好んで寄ってくることから欧米ではフルーツフライと呼ばれています。
ショウジョウバエについては「ショウジョウバエが発生する原因とは?ショウジョウバエの習性を知って対策しよう」でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
ノミバエ
| 全長 | 約2~3ミリメートル |
|---|---|
| 体色 | 褐色、黒褐色 |
| 種類数 | 約1600種類 |
ショウジョウバエに比べ頭や翅、体はやや細めで、ノミのように後ろ脚が長く背中部分が丸い体型をしています。ほかのコバエ類に比べて動きが速いため退治しにくい種類です。
アメリカでは、アリの体内に卵を産みつけて寄生する「ゾンビバエ」と呼ばれるノミバエの一種が、ヒアリの駆除に応用されています。
キノコバエ
| 全長 | 約2~3ミリメートル |
|---|---|
| 体色 | 黒色、灰黒色 |
| 種類数 | 約4500種類 |
| 日本で確認されている種類数 | 約250種 |
キノコバエは湿気が多く薄暗いところを好み、腐った植物などをエサとしています。メスよりもオスの方が活発に飛び回る習性があります。
キノコバエについては「キノコバエが発生する原因とは?キノコバエの対策と駆除方法について」でも詳しく解説しているため、併せてご覧ください。
チョウバエ
| 全長 | 約1~5ミリメートル |
|---|---|
| 体色 | 黒色、灰色 |
| 日本での種類数 | 約50種 |
ほかのコバエとは異なり、うちわ型の大きな翅を持っているのがチョウバエの大きな特徴です。トイレなどでよく見かけるため「便所バエ」とも呼ばれています。体の全体が細かい毛で覆われていて、ほかのコバエに比べると比較的ゆっくり飛ぶ傾向があります。
一般的に多く見られるのはオオチョウバエです。静止時には開いた両方の翅の形がハートの形に見えます。
オオチョウバエのほかに人家で生息するのは、体長1~2ミリメートルのホシチョウバエです。
チョウバエについては「チョウバエが発生する原因とは?チョウバエの退治方法と予防対策」でも詳しく解説しているため、併せてご覧ください。
コバエのライフサイクル
コバエは卵から幼虫、さらにサナギへと変わり成虫になります。
コバエの種類によってライフサイクルが異なるため、ここではショウジョウバエ(キイロショウジョウバエの場合)、ノミバエ(コシアキノミバエの場合)、キノコバエ、チョウバエについて説明します。
ショウジョウバエ
| 羽化後産卵までの期間 | 2日目以降 |
|---|---|
| 卵から成虫まで | 約10日 |
| 一度に産み付ける卵の数 | 1日30~50個程度 |
| 生涯産卵数 | 約500個 |
| 成虫の寿命 | 30日~60日 |
ノミバエ
| 羽化後産卵までの期間 | 3日目以降 |
|---|---|
| 卵から成虫まで | 約2週間 |
| 一度に産み付ける卵の数 | 30~40個を何度も生むことが可能 |
| 成虫の寿命 | 約10日 |
キノコバエ
| 羽化後産卵までの期間 | 2~3日目以降 |
|---|---|
| 卵の期間 | 約7日 |
| 幼虫の期間 | 8~20日 |
| 蛹の期間 | 3~5日 |
| 生涯産卵数 | 100~200個 |
| 成虫の寿命 | 約4~10日 |
チョウバエ
| 羽化後産卵までの期間 | 3~4日目以降 |
|---|---|
| 卵の期間 | 約2日 |
| 幼虫の期間 | 約10~14日 |
| 蛹の期間 | 約3~4日 |
| 生涯産卵数 | 平均240個 |
| 成虫の寿命 | 約4~14日 |
コバエによる被害

温かい時期に部屋で過ごしていて、なんとなく気になるのが「コバエが飛び回る」ことです。特に視界に入る範囲で常に飛び回られると不快に感じます。
今現在、日本で生息が確認されているコバエの種類は直接、人間に危害を与えている虫ではありません。ただし、生活上間接的に被害を及ぼす場合があります。
病気の媒介
コバエの仲間は特定の病原菌やウイルスを媒介するわけではありません。しかし、ごみや腐敗した食べ物、汚物やヘドロなどを好む種類もいるため、それらで発生する病原菌などを運搬して健康被害をもたらす可能性があります。
ハエ蛆(うじ)症
「ハエ蛆症」は、蠅蛆症(ようそしょう)とも呼ばれ、ハエの幼虫(蛆虫)がヒトの体内や皮膚に入り込み、組織や体液を食べることによって引き起こされる感染症です。
ニクバエやキンバエなど通常のハエが原因となるケースが一般的です。しかし、コバエの仲間であるノミバエによって発症することも知られています。
ノミバエは食べ物に卵を産みつけることもあるため、体内に侵入した幼虫が胃や腸に刺激を与えて腹痛や下痢の症状を引き起こす可能性があります。
生きたチョウバエの幼虫が鼻や口、目、肛門、生殖器などから体の中に入り込んでハエ蛆症の症状を起こす例も報告されているため、食品の衛生管理には十分な注意が必要です。
【参考】ハエ|日本防疫殺虫剤協会
大量発生による不快感
コバエは非常に繁殖能力が優れています。
多くの種類のコバエは羽化後2~3日程度で産卵し、生まれた卵は2日程度で孵化、10日から2週間で羽化します。短期間で世代を繰り返すため、またたく間に大量発生する恐れがあります。
部屋の中をたくさんのハエが飛び回るのは不快そのものです。いったん増えると根絶するのは簡単ではありません。
コバエが発生する原因

一般的にコバエの活動が活発になるのは4月から11月ぐらいまでです。コバエが好む環境が揃うと、どこからともなくやって来て徐々に増えていきます。
コバエが発生する場所・原因は種類によって違います。
ショウジョウバエ
ショウジョウバエの主なエサは、熟した果物や常温保存していて一部に傷や腐っている箇所がある野菜、ワインなどのアルコール類、酒、みりん、酢といった調味料などです。生ゴミがある三角コーナーや蓋のないゴミ箱のゴミにも集まってきます。
ノミバエ
ノミバエが好むのは、生ゴミ、腐敗した肉や野菜、コーヒーかす、ペットの糞、昆虫や動物の死骸、トイレ、排水溝などです。特に生ゴミに好んで飛来する傾向があります。
キノコバエ
観葉植物の養分や観葉植物に生えているキノコなどがヒトの生活環境におけるキノコバエの主なエサです。室内の観葉植物の腐葉土にキノコバエが産卵して発生するケースもあります。
気温30度、湿度は70%ぐらいの高温多湿な環境を好むため、梅雨時期に多く発生するのが特徴です。
ほかには根腐れなどを起こした観葉植物や、花瓶などの取り替え忘れて腐った水も好むようです。
チョウバエ
屋外では湿地や沼などに生息していますが、人間の生活圏内では公衆便所や水たまり付近を好みます。
家庭内では排水溝や排水管などに発生する有機物のスカムを好んで食べるため、一般的に台所、お風呂、トイレ、洗面所などに発生する傾向があります。これらが主な発生元です。
コバエ対策①コバエの好む環境にしない
まずはコバエが集まったり繁殖したりする原因を取り除くのが重要です。【コバエが好む環境(発生元)を減らしていく】
- 生ゴミを入れるゴミ箱は蓋つきを使う
- 生ゴミは出しっぱなしにしないでゴミ箱へ
- 生ゴミは長期間ため込まずになるべく早めに廃棄する
- 野菜・果物・調理した食べ物はなるべく常温で保管しない(保管する場合は密封する)
- 食事後の食器はすぐに洗う
- 排水溝の汚れはこまめに掃除する
- 排水管の汚れは、パイプクリーナーなどを使用して定期的に清掃する
- 空き缶・空き瓶・ペットボトルは中身をしっかりとすすいで廃棄する
- 三角コーナーはなるべく使わない
- ペットのトイレ掃除はこまめに
- 室内の観葉植物は水をあげすぎず、根腐れがないかときどきチェックする
フマキラーの「コバエバリア」は、三角コーナーや排水口、ストレーナーなどの水回りでのショウジョウバエ発生予防に非常に便利です。一度スプレーするだけで、2日間コショウジョウバエをシャットアウトが可能です。
この製品は殺虫・忌避・発生予防のトリプル効果に加え、除菌・消臭効果もプラスされています。
化学的な殺虫成分を使用していないため、100%食品由来成分で作られており、キッチン周りでも安心して使用できます。
コバエ対策②コバエを侵入させない
屋外からのコバエの侵入を防ぐ対策も検討しましょう。
スキマ対策をする
窓の隙間からコバエが入ってくる可能性があります。隙間が気になるようであればスキマテープを活用することで、コバエの侵入をある程度防ぐことができます。
アミ戸を目の細かいものに換える
一般的なアミ戸の網目は18メッシュ(1.15ミリメートル)から20メッシュ(1.03ミリメートル)です。コバエは1ミリメートル程度の隙間からでも侵入する可能性があります。
コバエなどの害虫対策には、24メッシュ(0.84ミリメートル)が良いでしょう。
これよりも目を細かくすると、害虫対策としては有効ですが風通しが悪くなります。
虫よけ剤を使用する
窓のスキマを防いでも体の小さなコバエの侵入を完全に阻止するのは簡単ではありません。
コバエを寄せ付けなくするために最も有効な方法は虫よけ剤(忌避剤)の使用です。
虫よけ剤にはスプレータイプや吊り下げ型などいろいろな種類があります。
玄関や窓のスキマからの侵入を防ぐ
玄関や窓・ベランダに吊り下げるだけでコバエなどの侵入を抑止するタイプの薬剤があります。
玄関から侵入するユスリカ、チョウバエ、キノコバエにはフマキラーの「虫よけバリアブラック 3Xパワー 玄関用 1年」がおすすめです。ドアノブに吊り下げるタイプのため簡単に設置できます。ソーラーパワーと風の力を利用してしっかりと虫よけ効果を発揮。約1年間効果が持続します。
窓やベランダから侵入するユスリカ、チョウバエ、キノコバエの侵入防止にはフマキラー「虫よけバリア プレミアム 300日」が最適。ベランダの物干しざおやカーテンレールに吊り下げるだけで効果を発揮します。
アミ戸からの侵入を防ぐ
アミ戸の目のスキマからもコバエは侵入します。目の細かいものであれば侵入は防げますが、交換するのは大変です。
スプレータイプの虫よけ剤であれば、アミ戸にスプレーするだけで虫を居つかせない効果があります。
フマキラーの「虫よけバリア アミ戸窓ガラススプレー」現玄関用とは、気になる場所にスプレーするだけなので簡単。ユスリカ、チョウバエ、キノコバエやカメムシなどのイヤな虫を4ヵ月間居つかせません。速乾性に優れていてギラつきやベタつきを最小限に抑えられるため、アミ戸だけでなく、窓ガラスや玄関灯にも使用できます。
コバエ対策③発生したらすぐに駆除する
もし家の中でコバエが発生したときは、見つけ次第すぐに駆除することが重要です。
発生元となるコバエが好む場所をつくらないようにして、駆除と予防を同時に行うようにしましょう。
見つけたらすぐに殺虫剤で駆除する
コバエを見つけたらすぐに殺虫剤で駆除しましょう。フマキラーの「コバエワンプッシュ プレミアム」は、コバエに直接噴射すると羽ばたき防止効果ですぐに落下。コバエを見失っても、部屋にワンプッシュするだけで超微粒子の薬剤がすみずみまで広がり、コバエをまとめて退治できます。ゴミ箱や三角コーナーなどにスプレーしておけば、コバエの発生を1ヵ月予防可能です。
しつこいコバエはトラップで徹底駆除する
コバエを見かけるたびに殺虫剤で退治しても、またどこからともなくコバエが出現する可能性があります。そのようなときは、どこか見えない場所でコバエが繁殖しているかもしれません。このようなケースでは、家の中に発生源となりそうな場所がないか、徹底的にチェックしてください。
それでもコバエがいなくならないときは、トラップを利用するのがよいでしょう。
トラップタイプの製品は、コバエが好むニオイを利用して誘引します。コバエが出現する部屋に置くだけでコバエを捕まえられます。
フマキラーの「コバエ超激取れキューブ」は、ショウジョウバエ類、ノミバエ類の習性を徹底研究。形・色・香りのトリプル誘引でショウジョウバエ類、ノミバエ類を強力に誘引します。さらに、習性を利用した「マレーズトラップ方式」で容器の中に誘い込みます。誘引剤は食品由来の成分(お酢・お酒・アミノ酸調味料)を使用しているため、キッチンに置いても安心です。
チョウバエは水で流す
チョウバエは水周辺を好む割に、直接水がかかるのが苦手です。水をかけられると下に落ちてしまいます。
お風呂場などの壁にとまっているのを見かけた場合、手元に殺虫剤がなければシャワーで水をかけてそのまま流してしまいましょう。
まとめ

コバエは、発生する原因を知ることで被害を予防できます。
何よりも生ゴミなどを放置せず、清潔な住環境の維持が重要です。さらに、侵入経路を極力減らし、虫よけ剤などを利用してコバエが寄り付かないように工夫しましょう。
見かけたときに放置すると増えやすいため、見つけ次第すぐに駆除できるように殺虫剤を購入しておくと便利です。








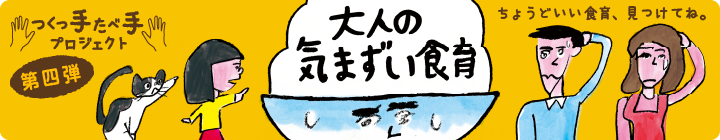
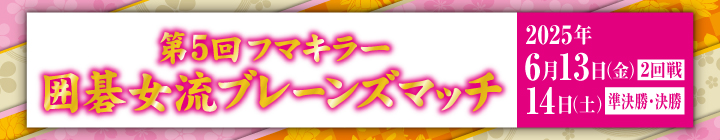

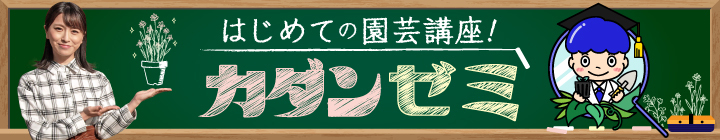
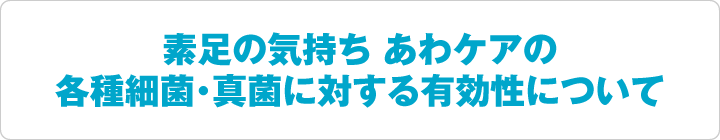
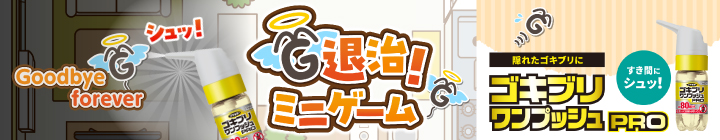
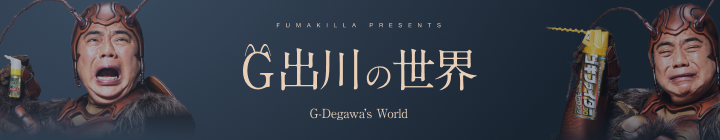






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



