2018年5月25日 | 虫
アリ(蟻)を見かける原因とは?アリの習性を知って対策しよう

私たちの生活圏内で、もっとも身近な昆虫の1つであるアリは「害虫」としてのイメージが薄いものの、基本的には集団で活動するため、住宅の周囲や室内で見かけると不快に思う人もいるでしょう。状況によってはアリに咬まれたり刺されたりすることもあります。また、近年では外来種の存在も問題になっています。
この記事では、身近な昆虫であるアリの生態や種類、アリによる被害、アリを見かける原因や場所、アリの予防と対策などについてご紹介します。
アリの生態と種類

はじめに、アリの生態についてご覧ください。
アリの生態
アリは卵から幼虫、サナギ、成虫と完全変態する昆虫で、分類上はハチの仲間に属します。サイズは1ミリメートルから4~5センチメートルくらいで、色は黒だけでなく黄や赤、黒とオレンジなどの二色、メタリックと多岐にわたります。アリの形状は、細長いものやずんぐりとしたものから、足が長いものまでさまざまです。
アリは「コロニー」と呼ばれる家族集団で生活をしています。体から特有のフェロモンを分泌して「警報」や「道しるべ」といった情報を仲間に伝えると考えられています。アリは小さくて弱い生き物のイメージがありますが、実は昆虫の中でも強い捕食者(ほしょくしゃ)として存在しています。
「シロアリ」はゴキブリの仲間に属すため、アリの仲間とは異なります。
女王アリと働きアリ
アリは、ハチやシロアリと同様に、それぞれが役割を持つ「社会性昆虫」です。コロニーの中に1匹の女王アリと働きアリからなる「単女王制のアリ」と複数の女王と働きアリからなる「多女王制のアリ」がいます。外来種であるイエヒメアリやヒアリ、アルゼンチンアリなどは多女王制のアリで、複数の女王がいることで繁殖力が高く問題視されています。アリは夏に繁殖する種が多く、風のない夕方に大きく成熟したコロニーから女王アリとオスのアリが同時に飛び立つ「結婚飛行」が行われるのです。女王アリはほかのコロニーのオスと出会い、交尾を行います。この交尾後、オスのアリは死んでしまいます。
女王アリの方は新しいコロニーをつくり、交尾で体内に貯めた精子を使い、長い寿命の間に何度も産卵を行うのです。
コロニーでは、卵から孵化した幼虫が働きアリに成長し、次に生まれる幼虫の世話をするパターンを繰り返してアリの数を増加させます。一部のアリは結婚飛行を行わず、ほかから飛んできたオスが女王アリのコロニーで交尾して繁殖します。
アリの主な種類
アリの種類は、世界でおよそ1万種類以上、国内で280種類以上が確認されており、日本だけに生息する固有種はおよそ120種類です。ここでは主要な種類と、重要な外来種についてご紹介します。
クロオオアリ
| 体長 | 約7~12ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 全体に黒く、頭部は光沢を欠く |
トビイロシワアリ
| 体長 | 約2.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 黒褐色で、頭部に縦のシワがある |
イエヒメアリ
| 体長 | 約2~2.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 全体的に淡い色で、腹部が薄い黒 |
オオズアリ
| 体長 | 約3〜4.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 頭部と腹部は黒く、それ以外の部分は赤褐色 |
ルリアリ
| 体長 | 約2ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 黒色で光沢がある |
アミメアリ
| 体長 | 約2.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 全体が茶褐色、腹部が黒褐色で丸みと光沢がある |
トビイロケアリ
| 体長 | 約2.5~3.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 全体が黒褐色、胸部だけ少し色が薄い |
外来種のアリ

近年では、コンテナなどを経由して外来種のアリが国内に侵入しています。外来種のアリは、攻撃性や毒を持つ種類がいるので注意が必要です。
アルゼンチンアリ
1990年代前半に広島県廿日市(はつかいち)市で発見されてから、日本で広く見られるようになった外来種です。1つのコロニーに複数の女王アリがいるため、繁殖力が非常に高く住み着かれると駆除が困難です。また、攻撃性の高さから在来種の生態系の維持が危ぶまれています。
| 体長 | 約2.5ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 多くは淡褐色、個体によっては褐色である |
| エサ | 雑食性であるが、砂糖や花の蜜、アブラムシやカイガラムシが分泌する甘露(かんろ)を好む |
| 主な営巣場所 | 植木鉢や石の下、ブロック塀(べい)やコンクリートのすき間や割れ目など |
アルゼンチンアリと思われるアリを発見したときは、自治体の担当課に連絡しましょう。
アルゼンチンアリについては、「【特定外来生物】アルゼンチンアリの生態・被害・対策について」で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
ヒアリ
2017年5月に兵庫県で初めて確認されました。以来、全国各地の港で発見されています。攻撃性が高く、刺されると患部が腫れて膿がたまることもあります。また、アナフィラキシーショックを起こす場合もあり、処置が遅れると命に関わる場合もあります。めまいや息切れ・動悸などのショック症状が出たらすぐに病院に行きましょう。
ヒアリの一部は、羽を持つアリに成長して別のコロニーをつくるため、アルゼンチンアリに比べると、分布の広がりが早いと指摘されています。
| 体長 | 約2.5~6ミリメートル |
|---|---|
| 特徴 | 全体は赤褐色で、腹部は黒がかった赤色 |
| エサ | 雑食性で花蜜や種子、ほかの虫、小動物なども捕食する |
| 主な営巣場所 | 道路わき、牧草地、芝生、公園など |
ヒアリと思われるアリを見つけた場合は刺されないように注意しながら、自治体や地方環境事務所に連絡しましょう。
ヒアリについては、「【特定外来生物】ヒアリの生態・被害・対策について」で詳しく解説していますので、ご覧ください。
アリの被害について

次に、アリによる被害についてご紹介します。
住宅への侵入被害
住宅に侵入したアリは、食品に被害を与えるので気をつけましょう。アリの種類によっては、食品の袋を破って中身を食べることがあります。特に砂糖などの食品に集まることが多いです。また、アルゼンチンアリが赤ちゃんの口元に残ったミルクに集まっていたという事例も報告されています。
このように、アリは人の生活圏に入ると、的確に食べ物を見つけて群がることがありますので、注意が必要です。
人への直接的被害
アリはまれに人を咬んだり刺したりすることがあります。特に国内では、ヒアリに刺された事例が報告されています。このためアリを見つけた際には、むやみに触らないようにしましょう。また、アリの中にはハチのように針を持った種類も存在します。好奇心旺盛なお子さんがいる家庭では、十分注意してください。アリに触れたり近づいたりすることで、事故が起こる可能性があります。
アリの集団行動が生理的な嫌悪感を招くケースも少なくありません。
農作物への被害
農作物に大きな被害をもたらすアブラムシやカイガラムシのなかには、アリと共生関係にあるものもいます。アリはアブラムシやカイガラムシが分泌する甘露を好み、アブラムシなどの天敵であるテントウムシを攻撃します。その結果、農作物の被害が助長されます。
アルゼンチンアリは、多くの都府県でも活動範囲が広まっています。アルゼンチンアリ自体も果実などの農作物に被害をもたらすため、今後は国内の農業に大きな影響を及ぼすかもしれません。
【参考】アルゼンチンアリの被害 – 廿日市市公式ホームページ
アリが巣を作る場所と原因

続いて、アリが巣を作る場所と原因についてご紹介します。
アリをよく見かける場所
アリが住宅に侵入してくる目的は、エサの確保です。食品や食べこぼしはもちろん、歯磨き粉や歯磨き粉の残った歯ブラシなどにも集まることがあります。住宅でアリが発生しやすい場所はキッチンやリビング、洗面所などが該当するといえるでしょう。
アリはエサを見つけると、フェロモンを出して仲間を呼びます。アリの行列は、仲間が出すフェロモンをたどっていると考えられています。
巣を作りやすい場所
庭や芝生などで見かける小さな土の山は、蟻塚(ありづか)と呼ばれます。蟻塚はアリがコロニーをつくる際に掘った土が集まったもので、コロニーを見つける目印です。アリのコロニーは、植木鉢や芝生の下などにも存在します。
住居内に侵入の形跡がなくても、庭や敷地内にコロニーがあれば、アリが住宅内外をエサ場にしている可能性があります。また、アルゼンチンアリは小さなすき間や亀裂のほか、段ボールの下や空き缶の中などにコロニーをつくることがあります。
アリの予防と対策

以上を踏まえながら、アリの予防と対策についてご紹介します。以下の方法は、駆除した後に再発を防止するアフターケアとしても有効です。
部屋の清掃
食べこぼしなどがあると、アリが群がることになります。フローリングやカーペット、畳などは、こまめに掃除機をかけるなどして清潔を保ちましょう。特に、小さなお子さんやペットと暮らす家庭は、食べこぼしに注意してください。
食品類の保存
アリが好む砂糖や菓子などの袋は、しっかりと封をしましょう。使いかけ・食べかけの食品を保存容器に入れ替えても構いません。歯磨き粉もしっかりと蓋(ふた)を閉めて、液体タイプは中身がこぼれないように注意してください。
生ごみの処理
三角コーナーに生ごみを放置したり、生ごみを保管するごみ箱の蓋を開けたままにしたりするとアリが群がることがあります。調理の際に出た生ごみは、ビニール袋に入れてしっかりと口を結び、回収日まで保管しましょう。
食器類の洗浄
アリは、食器や鍋(なべ)などについた洗い残しや焦げ付きに集まることがあるので、日頃からていねいな洗浄を心がけてください。また、使い終わった食器類をキッチンに放置せず、こまめに洗うようにしましょう。
すき間の対策
体が小さいアリは、わずかなすき間から住宅内に侵入します。壁のすき間はシーリングなどを、窓や換気扇のすき間はテープなどを利用してふさいでください。配管や配線の穴などは見落としがちであるため、あらためて住宅内をチェックしましょう。
屋外の管理
住宅外の通路や庭では、植木鉢などを土の上に置かないようにするだけで営巣の危険性を減らせます。また、土の上に敷いている防水シートや芝生などは、土の状況を確認して定期的にお手入れしてください。
アリを駆除する方法
最後に、アリを駆除する方法についてご紹介します。
部屋に侵入したアリの駆除
室内でアリを見つけたときは、ティッシュペーパーでつまむなどしてすべて駆除してください。触るのが苦手という場合は、殺虫スプレーを使うとすぐに駆除できます。殺虫スプレーは、アリが飛び散らないように噴射を調節したタイプもあります。ただし、殺虫スプレーを使用するときは、小さなお子さんやペットなどを退避させてから散布してください。
駆除した後は、アリが侵入したルートやすき間を調べて、再発を防ぐために忌避剤(きひざい)を使用しましょう。忌避剤は、スプレーや粉のタイプ、置くタイプなどが販売されています。
コロニーの駆除
コロニーの場所は、アリの行列や蟻塚を頼りにして特定してください。コロニーを駆除する薬剤は、直接かけるスプレーやシャワーのタイプ、粉のタイプ、置くタイプなどがあります。
アルゼンチンアリの対応については下記を参考にしてください。
【参考】環境省「アルゼンチンアリ防除の手引き」
まとめ
今回は、アリの生態や種類、アリによる被害、アリを見かける原因や場所、アリの予防と対策などについてご紹介いたしました。住宅内では食品や生ごみの管理などを心がけ、アリが侵入しそうなすき間も対策しましょう。
アリを見つけたら早急に駆除して侵入ルートやコロニーを特定し、忌避剤などを使用して再発を防いでください。外来種のアルゼンチンアリやヒアリと思われるアリを発見したときは、すみやかに自治体などに連絡しましょう。
(確認用)アリサイズ参照元
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F80902.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F40902.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F41107.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F40605.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F70201.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F42001.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F80603.html
http://ant.miyakyo-u.ac.jp/J/Taxo/F90012.html








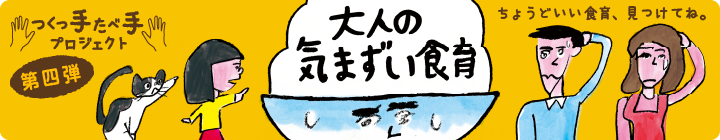
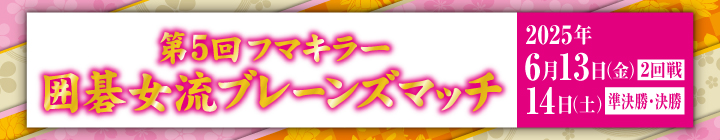

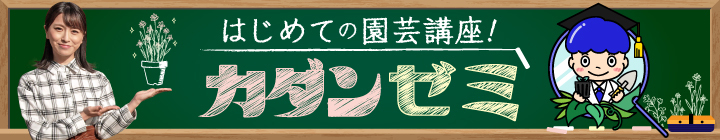
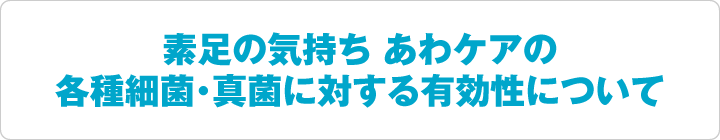
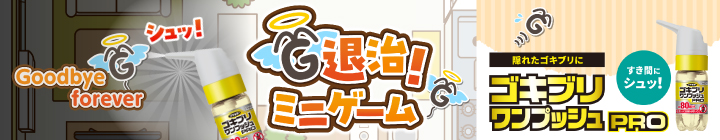
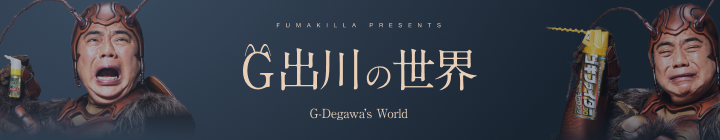






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



