2025年9月16日 | お役立ち情報
世界遺産「熊野古道」とは?おすすめコースや注意点を解説

熊野古道は、2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録された世界遺産の一部です。登録以降、多くの人が訪れてウォーキングを楽しんでいます。一度歩いてみたいけれども、どこを歩けばいいのかわからないと思っている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、熊野古道の歴史やおすすめのコースをわかりやすく紹介します。歩く際の注意点も解説するので、ぜひご覧ください。
熊野古道とは?
熊野古道は、紀伊半島各地から熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)へ続く参詣道の総称で、熊野参詣道とも呼ばれます。
熊野三山は、平安時代後期から、神の宿る神聖な場所として皇族、貴族から庶民に至るまで、多くの人が参詣に訪れました。当時の都である京都をはじめ、さまざまな地域から熊野を訪れるためにいくつかのルートが整備されてできたのが熊野古道です。
京都や大阪、伊勢から熊野へ続く道として和歌山、三重、奈良にまたがり、その全長は約1,000キロメートルに及びます。
熊野古道を含む「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録

熊野古道は、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、2004年に世界遺産に登録されました。世界遺産には、熊野三山と熊野古道のほか「高野山」と「吉野・大峯」、さらにそれらの霊場を結ぶ「高野参詣道」「大峯奥駈道」が含まれています。
世界遺産とは、「顕著な普遍的価値」を持つ自然や遺跡、建築物などを人類の共通の財産として未来に残すべきものとしてユネスコが認定したものです。「紀伊山地の霊場と参詣道」は、日本では12番目の世界遺産であり、2025年9月現在、日本には26の世界遺産が登録されています。
世界遺産に登録された背景
「熊野三山」「高野山」「吉野・大峯」の3つの霊場は、日本古来の自然崇拝に基づく神道と中国から伝来した仏教が結び付き、1,200年以上にわたって信仰の対象となってきました。単なる歴史的建造物と道ではなく、多様な宗教文化と独自の精神文化を形成し、自然と一体となって人々の意識と生活に溶け込んだ存在であることが世界遺産に認定された理由です。
世界遺産登録後の変化
世界遺産登録後は、和歌山、三重、奈良の3県が連携し、参詣マナーや歩行ルートに関するルールを定め、休憩所の整備を進めてきました。
さらに各地でさまざまなイベントも開催され、観光客数が大幅に増加しています。熊野古道全体の来訪者数は正確に把握できていませんが、主要ルートのひとつである伊勢路では、登録前の2003年に約10万人の来訪者が、2023年は約30万人と3倍になりました。
熊野古道の主要6ルート
熊野古道は、京都・大阪、高野山、伊勢と熊野三山を結ぶルートとして、主に6つのルートに分かれています。
紀伊路(きいじ)
- ルート:渡辺津(わたなべのつ)〜田辺
- 距離:約120キロメートル
紀伊路は、淀川河口の渡辺津(現在の大阪市天満橋付近)から、紀伊半島の西端を南に下り、紀伊田辺に至るルートです。道中には、安珍・清姫の物語で知られる道成寺(どうじょうじ)や紀三井寺などの歴史ある寺社、「絶景の宝庫」として万葉集にも詠まれた吹上の浜(和歌の浦)などの景勝地があります。
中辺路(なかへち)
- ルート:田辺〜熊野三山
- 距離:約84キロメートル
紀伊田辺から、本宮(熊野本宮大社)、新宮(熊野速玉大社)、那智(熊野那智大社)に至る熊野古道の最もメインとなるルートです。狭義の熊野古道は、主に中辺路を指します。
険しい山道が続く道で、平安時代、鎌倉時代には山岳修業として貴族などが繰り返し参詣しました。
小辺路(こへち)
- ルート:高野山〜熊野三山
- 距離:約70キロメートル
高野山と熊野を結ぶ最短ルートで、高野街道とも呼ばれます。標高1,000メートル級の山を越えなければならない険しい道のりです。途中には、「源泉掛け流し」で有名な十津川温泉があります。
大辺路(おおへち)
- ルート:田辺〜那智勝浦
- 距離:約120キロメートル
田辺市から那智勝浦まで続く、紀伊半島南部の海沿いの道が、大辺路です。江戸時代に紀州藩によって、整備された比較的新しいルートです。道中には、古木が立ち並ぶ山道と大小約80の奇岩が850メートルにわたって並ぶ景勝地「橋杭岩(はしぐいいわ)」が見どころのひとつです。
伊勢路(いせじ)
- ルート:伊勢神宮〜熊野三山
- 距離:約160キロメートル
伊勢路は、伊勢参宮を終えた後、西国三十三カ所を巡礼する旅人が通った道で、江戸時代以降に栄えました。当時、伊勢も熊野も庶民にとっての信仰の中心で何度も訪れたい場所であり、「伊勢に七度、熊野に三度」ということわざがあったほどです。
道中には険しい峠がいくつかありますが、峠道から望む海や石畳、棚田など昔ながらの美しい景観が味わえます。
大峯奥駈道(おおみねおくがけみち)
- ルート:吉野・大峯〜熊野三山
- 距離:約170キロメートル
世界遺産に登録されている修験道の聖地である吉野・大峯と熊野三山を結ぶルートです。熊野古道は、本来修験者が修行する道であるため、道中には行場(ぎょうば)と呼ばれる修験者が修業をする場所が75ヵ所設けられています。
修験者が通る道だけあって、道中は1,200メートルから1,900メートル級の険しい山の稜線を進みます。
熊野古道の見どころ
熊野古道には、本来の目的地である熊野本宮大社をはじめ、多くの見どころがあります。
熊野三山
熊野三山とは、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の3つの神社の総称です。それに加えて、那智山青岸渡寺を含む場合もあります。
熊野本宮大社は、熊野三山の中でもとりわけ重要な位置にあり、全国に4,700以上ある熊野神社の総本宮です。檜皮葺の社殿と周りにそびえる杉の巨木が歴史の重みを感じさせます。
熊野速玉大社は、熊野本宮大社とは対照的な鮮やかな朱塗りの宮殿がひときわ目を引き、境内には樹齢1,000年を超えるご神木・ナギの木があります。敷地内にある神宝館(しんぽうかん)には、主に室町時代に集められた1,200点以上の国宝が保管されています。
熊野那智大社は、創建されたのがはるか1,700年前。仁徳天皇の時代と言われています。462段の石段を上った先に、6棟の朱塗りの社殿があり、境内には日本サッカー協会のシンボルとしても知られる3本足の八咫烏(やたがらす)が祀られていることでも有名です。
大斎原(おおゆのはら)

大斎原には、高さ約34メートル、幅42メートルの日本最大の大鳥居があります。ここは、もともと熊野本宮大社があった場所で、1889年(明治22年)の大水害で社殿が流出したため、約500メートル離れた現在の場所に遷座しました。
近年は、桜の名所やパワースポットとしても有名で、多くの人が訪れます。
那智の滝
那智の滝は、日本三名瀑の一つ、那智山の奥から流れる落差133メートルの滝です。滝の幅は13メートル、滝壺の深さ10メートル、毎秒約1トンの水が流れ落ちる様子は迫力満点です。滝の近くに御滝拝所舞台が設営されていて、間近で眺められます。
滝壺の水を飲むと延命長寿のご利益があるとされています。
熊野古道のおすすめウォーキングルート

全長1,000キロメートルに及ぶ熊野古道の全てを歩いて踏破するのはたいへんです。この項では、初心者でも手軽に楽しめるおすすめのウォーキングルートをいくつか紹介します。
発心門王子~熊野本宮大社
- 発心門王子〜水呑王子〜伏拝王子〜三軒茶屋跡〜熊野本宮大社
- 全長約7キロメートル、歩行時間5〜3時間
熊野古道のゴールデンルートとも呼ばれる、中辺路のルートです。熊野古道に数あるウォーキングコースの中で、最も人気のあるコースと言えるでしょう。緩やかな傾斜で、初心者でも歩きやすいのが特徴です。
発心門王子(ほっしんもんおうじ)は、熊野本宮大社の神域の入り口とされています。道中、石畳の残る道や茶畑などがあり、休憩所やトイレも整備されています。
大門坂〜那智の滝・熊野那智大社

- 大門坂〜多富気王子〜熊野那智大社・熊野青岸渡寺〜那智の滝
- 全長約3キロメートル、歩行時間5〜2時間
このコースは中辺路の一部で、熊野那智大社付近を歩くルートです。大門坂は、樹齢800年を超える杉に囲まれた全長約500メートルの美しい石畳で、石畳を登りきると、熊野那智大社があります。
熊野那智大社に祀られている神様は、人の縁やさまざまな願いごとを結ぶとして多くの人が参拝する神社です。
熊野那智大社から1分ほどの場所には、熊野青岸渡寺(くまのせいがんとじ)があります。熊野那智大社が美しい朱塗りの社殿であるのに対して、青岸渡寺の本堂は天然木の素朴な質感の「素木造り」です。さらに徒歩15分ほどで、朱塗りの三重塔と日本最大の落差を誇る那智の滝を見ることができます。
大日越
- 熊野本宮大社〜大斎原〜大日越〜湯の峰温泉
- 全長約4キロメートル、歩行時間1~1.5時間
大日越も中辺路のルートのひとつで、熊野本宮大社と湯の峰温泉を結ぶ山越えのコースです。距離は比較的短いものの、アップダウンが激しいのが特徴です。
熊野本宮大社から大斎原の大鳥居をくぐり、大日越の坂を登ります。坂の途中には、樹齢300年を超える巨木にたたずむ月見ヶ丘神社があります。
ゴールの湯の峰温泉は、日本最古の湯といわれており、旅の疲れを癒すのにぜひ浸かってみてください。
熊野古道を歩く際の注意点
熊野古道は世界遺産の一部です。美しい景観を保持し、安全に歩くために注意が必要です。
景観の保全に協力を
熊野古道のエリアの多くは世界遺産に指定されています。
・熊野本宮観光協会では、貴重な自然と景観を守るために、以下のような「紀伊山地の参詣道ルール」を定めています。
| 1. 「人類の遺産」をみんなで守ります
2. いにしえからの祈りの心をたどります 3. 笑顔であいさつ、心のふれあいを深めます 4. 動植物をとらず、持ち込まず、大切にします 5. 計画と装備を万全に、ゆとりを持って歩きます 6. 道からはずれないようにします 7. 火の用心をこころがけます 8. ゴミを持ち帰り、きれいな道にします |
虫・動物に注意
熊野古道には、鬱蒼とした森を抜けるルートも多く、さまざまな動物に遭遇するおそれがあります。
マムシ
マムシに咬まれた場合は、激しい痛みや腫れが生じます。咬まれたら、あわてずに噛まれた部位を心臓より低くして動かないようにしましょう。その後、速やかに救急車を呼ぶか、医療機関を受診してください。自己判断で毒を絞り出したり、傷口を縛ったりするのは避けましょう。
スズメバチ
スズメバチは木の枝に巣を作ることが多いですが、オオスズメバチは土の中や木の洞にもよく巣を設けます。スズメバチの巣に近づかないように設定されたルートから外れずに歩きましょう。
スズメバチに刺されると赤く腫れ、激しい痛みがあります。指された場合は傷口を流水で洗い、じんましんやめまいなどのアレルギー症状が出たら、すぐに医療機関を受診してください。
ムカデ
ムカデは湿気を好み、梅雨時などに活発に活動します。夜行性のため、日中咬まれることは少ないですが、注意は必要です。
咬まれた場合は、傷口を流水で洗い流してしばらく様子を見ます。めまいや吐き気などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診する必要があります。
マダニ
マダニは、草むらなどに潜んでいて動物が付近を通るときに寄生します。マダニは、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)という重篤な病気を媒介します。SFTSは致死率が高く(27パーセント程度)、特に高齢者は注意が必要です。
過去10年ほどでSFTS感染者は増加傾向にあり、2025年は8月の時点で、すでに前年度の患者数を上回っています。
熊野古道を歩く際は、なるべくルートから逸れないこと、皮膚の露出を極力抑えることが重要です。
ツキノワグマ
近年は、全国的にクマの目撃情報・被害情報が増えています。熊野古道のエリアでも、主に中辺路を中心に毎年多数のクマ目撃情報があります。具体的な被害はほとんどありませんが、2024年8月には、三重県ツヅラト峠付近(伊勢路)で女性がツキノワグマにおそわれ、重傷を負いました。
その他の注意点
上記の紀伊山地の参詣道ルール」以外に、和歌山県世界遺産センターでは、以下の点にも注意を呼びかけています。
| ・ストックの先端にはゴムキャップを着用
・スパイク付きの靴や底の硬い靴は使用しない ・自転車、バイクなどで走行しない ・事前に参詣道の情報を収集する |
熊野古道を歩くための準備・服装・持ち物
熊野古道には初心者でも気軽に歩けるコースがありますが、中には標高1,000メートルを超えるルートやアップダウンの激しい山道もあり、しっかりとした準備が必要です。
無理のない計画と事前の情報収集
熊野古道を歩く際は、事前に十分に情報収集を行い、無理のない計画を立ててください。さまざまなルートがあるため、日程や体力などに余裕のあるプランにしましょう。
どの時期に行くかも重要です。時期によっては、暑さ対策や日没の時間も考慮しなければなりません。当日の天気予報やクマの目撃情報なども要チェックです。
十分な体調管理
歩く日の前日までに、しっかりと体調を整えておきましょう。体力に不安がある場合は、体力作りも必要です。当日、体調があまりよくなければ中止する決断もしなければなりません。
特に夏場は体調管理に十分気をつける必要があります。水分(できればスポーツドリンクなどで電解質も一緒に摂取する)補給をこまめに行い、日陰で休憩しながら歩くよう心がけてください。
ウォーキング時の服装
ウォーキングコースとはいえ、基本的にはトレッキング(山頂を目指さない軽い山歩き)の服装をした方が良いでしょう。藪などを歩く際に露出している部分をケガすることがあります。また、マダニも露出した肌に寄生するため、真夏でも肌を露出しない服装が基本です。
山深い場所だけでなく、開けたエリアもあるため温度・日差しの変化に対応できる服装にする必要があります。雨対策にカッパなども準備しましょう。
ウォーキング時の持ち物
| ・リュックサック
・飲料水 ・携帯電話(電波が届かない場所もあるため要注意) ・地図 ・補助食 ・地図 ・手袋 ・携帯用の救急セット ・虫よけスプレー |
自然豊かな熊野古道を歩く際には、虫よけ対策が重要です。フマキラーの「天使のスキンベーププレミアム」は、虫よけ成分「イカリジン」を高濃度に配合。虫よけ効果は最大8時間持続するため、長時間のウォーキングにも便利です。蚊、アブ、マダニ、ヤマビルなど、熊野古道のウォーキングや山歩きで遭遇する多くの虫に効果があります。
まとめ
この記事では、熊野古道の歴史やおすすめのコースを紹介しました。休憩所なども整備され、初心者でも気軽に楽しめるコースがあります。ぜひ熊野古道の魅力を自分の脚で確かめてください。
とはいえ、熊野古道はかつては修験者の修業の場でもありました。標高1,000メートルを超える山や険しい坂道もあるため、事前の準備が必要です。特に暑い時期には、水分補給と虫よけ対策をしっかりと行いましょう。








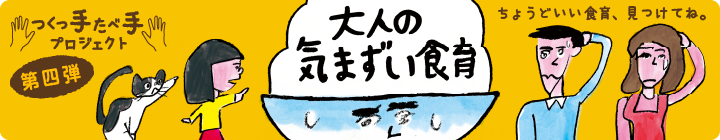
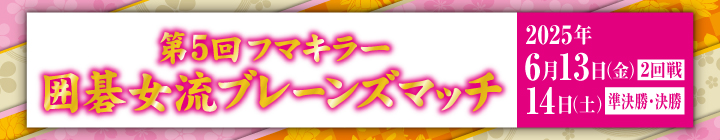

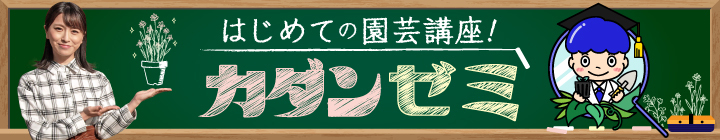
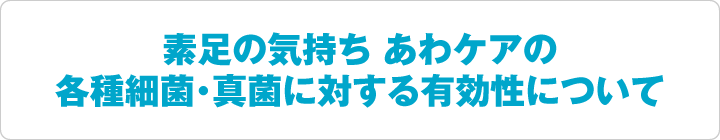
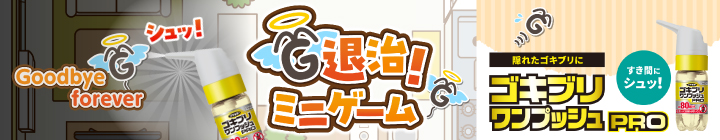
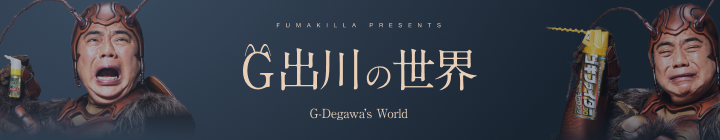






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



