2018年2月15日 | 虫
ハエ(蠅)が発生する原因とは?ハエの習性を知って対策しよう

害虫の中でも身近な存在であるハエは、不快で不潔な印象を与えるだけではなく、病原菌やウイルスを運ぶ「衛生害虫」として、人や動物にさまざまな被害をもたらすため、注意が必要です。
この記事では、ハエの生態と主な種類、ハエによる被害、ハエが発生しやすい場所と原因、さらにハエの予防と対策についてご紹介します。日々のハエ対策にぜひお役立てください。
ハエの生態と種類

はじめに、ハエの生態と種類を理解しましょう。
ハエの生態
日本国内では、およそ3000種類も生息していると言われるハエ。ハエは卵から幼虫、サナギ、成虫へと成長する「完全変態」の昆虫です。卵から成虫になるまでの期間は約2週間です。ハエは生息する場所へ直接卵を産み付ける習性があります。身近なハエの一種、イエバエは一度の産卵で50~150個の卵を産み、一生に500個以上の卵を産むことが知られています。このようにイエバエは非常に高い繁殖力があるため、大量発生することが珍しくありません。
特に、温暖な季節には、成長スピードが早まるため、気温が上がる時期には注意が必要です。また、ハエは動物の排泄(はいせつ)物、死骸(しがい)、腐った食品などの腐食(ふしょく)物質からタンパク源を摂取して繁殖しますが、これらの物質の多くには、寄生虫やウイルスが繁殖しています。
ハエの体には病原体が付いている可能性が高いため、生活圏に入り込んできた場合はすぐに駆除しましょう。
身近なハエの種類
わたしたちの身近には多数のハエが存在しますが、害虫として忌み嫌われているものは一部です。ここでは、身近で見かける主なハエをご紹介します。
イエバエ
わたしたちが最も目にしているハエはイエバエでしょう。イエバエは主に人の生活圏に生息しており、自然界で見ることはほとんどありません。
| 体長 | 6~9ミリメートル |
|---|---|
| 色 | 灰・褐色 |
| 特徴 | 胴体に縦じま |
| 活動エリア | 住宅の食品が置いてある場所やトイレ・飲食店・ゴミ置き場など |
| エサ | 動物の排泄物・腐った食品 |
センチニクバエ
日本全土に分布していますが、北海道などの寒い地域には少ないと言われます。センチニクバエは、主に夏場に集中して発生します。
| 体長 | 8~14ミリメートル |
|---|---|
| 色 | 灰色 |
| 特徴 | 胴体に市松模様 |
| 活動エリア | 住宅のトイレ・ゴミ置き場など |
| エサ | 動物の排泄物・動物死骸・腐った食品 |
オオクロバエ
国内ではイエバエと並び、よく見られる種類です。オオクロバエは人の生活圏だけではなく、高山などの自然界でも生息しています。
| 体長 | 7~14ミリメートル |
|---|---|
| 色 | 藍・黒色 |
| 特徴 | 胴体が灰白粉で覆われている |
| 活動エリア | 住宅や公衆のトイレ・ゴミ置き場など |
| エサ | 動物の排泄物 |
ヒメイエバエ
ヒメイエバエは、イエバエ、オオクロバエと同様に人の生活圏で活動します。天井や壁などに静止する・群れて飛ぶなどの習性があります。
| 体長 | 4~7ミリメートル |
|---|---|
| 色 | 黒、または灰色 |
| 特徴 | 細長・小型で胴体に3本の縦じま |
| 活動エリア | 台所・トイレ・蜂の巣など |
| エサ | 熟した果実・動物の死骸や排泄物 |
ショウジョウバエ(不快害虫)
俗に「コバエ」と呼ばれるハエで、野外や住宅などに幅広く存在します。ショウジョウバエは感染症の媒介はしないと考えられていますが、一生で500個以上の卵を産み、繁殖力が強いので注意しましょう。
| 体長 | 2~5ミリメートル |
|---|---|
| 色 | 黄褐色・赤褐色・黒褐色 |
| 特徴 | 体が小さく赤い目を持つ |
| 活動エリア | 台所・ゴミ置き場・樹木の果実など |
| エサ | 熟した果実・発酵した物質 |
ハエの被害について
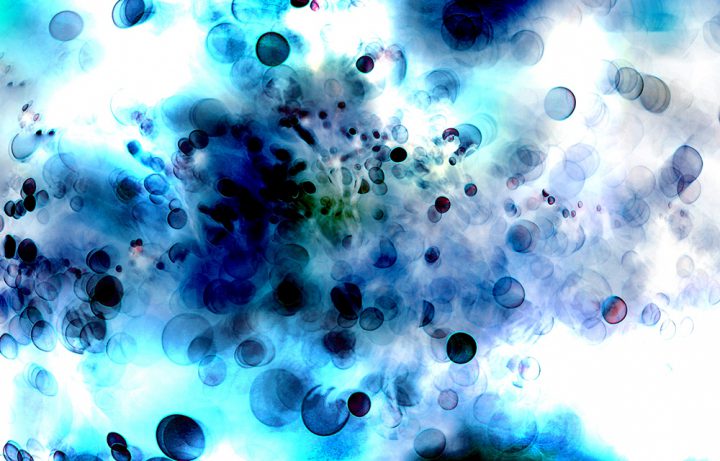
続いて、ハエの被害についてご紹介します。
病原菌の媒介(ばいかい)
先述のとおり、ハエは蛋白源としている動物の排泄物や腐敗した食品、動物の死骸などを通じて感染症を媒介します。具体的には、ウイルスや寄生虫の卵などをハエの体の表面に付着して運ぶ、食品に体液を吐き出す、食品に排泄するなどの経緯で広まります。
近年では、都心部を中心に衛生環境が向上したことで、以前よりもハエが少なくなりました。しかし、1990年代後半の病原性大腸菌のO-157や、2004年の鳥インフルエンザといった重大な感染症はハエによる媒介の可能性が高いと報告されたため、再び警戒が呼びかけられています。
【参考】
厚生労働省「ハエ類の腸管出血性大腸菌保有状況に関する全国調査結果について」
国立感染症研究所「2004年高病原性鳥インフルエンザ国内流行地で採集されたクロバエ類からのH5N1亜型インフルエンザウイルスの検出と分離」
ほかにも、ハエはコレラ、チフス、赤痢といった病原菌、ポリオウイルス、皮ふや目の疾患に関わる病原体、寄生虫の卵などを媒介すると言われています。
【参考】日本防疫殺虫剤協会「ハエ」
また、ヒトには感染しませんが、豚熱(ぶたねつ)と呼ばれるブタの感染症のウイルスをハエが運ぶ可能性も報告されています。
【参考】小笠原 悠「クロバエによる豚熱ウイルスの伝播リスク評価」
不快感や風評被害
ハエが飛び回る状況は、不快な気分を与えるだけでなく、不潔な空間といったイメージをもたらします。特に衛生面が重視される飲食店では、ハエの存在が風評被害や売り上げの低下などにつながりかねません。ハエの発生状況によっては、保健所からの指導や営業停止処分が下されることもあります。
ハエが発生する場所と原因

次に、住宅内でハエが発生しやすい場所と原因についてご紹介します。
台所・居間
食品や生ゴミを扱う台所や居間は、特にハエが発生しやすい場所です。イエバエなどのハエは、腐敗した食品や強いニオイを好むため、これらの場所で活動し、食品や生ゴミに直接卵を産み付ける危険があります。
ペット住居スペース
ペットを飼っている家庭も要注意です。ペットの残飯や、室内、庭の排泄物にもハエが寄り付きます。衛生面だけではなく、ペットの感染症を予防するためにもハエに対する警戒を怠らないようにしましょう。
ゴミ保管スペース
屋内外で生ゴミを保管しているゴミの保管スペースは、ハエが発生しやすい場所です。ハエは腐敗した食品や排泄物をエサとするため、ゴミ保管スペースは卵を産み付ける危険性が高まります。夏場はゴミのニオイが強くなるだけでなく、空調が行き届かずに温度が上がるため、ハエが大量発生する可能性があります。
ねずみの巣
住宅内に住み着いたねずみの排泄物や死骸にハエが集まり、卵を産み付けることもあります。ねずみは天井や壁内、床下などの目立たない場所に巣をつくるため、住人が気付かない間にハエが大量発生するケースも否定できません。
ハエの予防と対策

以上を踏まえて、住宅内のハエの予防と対策を行いましょう。基本的には、エサになるものを放置しない・繁殖に適した環境をつくらないことがポイントです。
外からの侵入対策
イエバエをはじめとするハエは、積極的に人間の住居エリアに入り込んできます。ゴミを外に放置しない、隙間にネットを張るなどの方法で、まずはハエを寄せ付けないこと、外からの侵入を防いで繁殖させないことが大切です。
このような対策はさまざまな害虫や害獣などの侵入も防止し、二次被害としてのハエの繁殖も予防できます。暑い季節は網戸などで住宅の風通しが必要ですが、同時にハエをはじめとした侵入者を呼び寄せない対策も心がけましょう。
台所・居間対策
食品を放置しない、調味料などの開封口を開けっ放しにしない、食べかすが付いたゴミを置かないなどの基本的な予防はもちろん、三角コーナーのゴミもこまめに片付けて清潔を保ってください。使用した食器にも雑菌が繁殖するため、放置しないようにしましょう。
また、夏に比べて寒い時期は害虫対策を怠りがちですが、越冬するハエも存在します。さらに、近年では住宅環境の向上や暖房器具の普及により、冬でも食品が腐ることがあるので注意してください。
ペット住居スペース対策
缶詰や肉・魚などの手作りのエサを与えている家庭では、残飯をこまめに掃除して、エサや水回りを清潔に保ってください。室内や庭などの自宅敷地内にペットのトイレを置いている場合も要注意です。ハエが寄り付かないように、できるだけ早めに片付けるなどして衛生環境を保ちましょう。
なお、猫はねずみや鳥の死骸を持ち込むことがあるので注意してください。
ゴミ保管スペース対策
ゴミの収集日まで保管しておくゴミ箱は、しっかりと蓋をすることはもちろん、ゴミ袋を2重にするなどの工夫をしましょう。小さなハエはわずかな隙間から侵入するので、生ゴミは1日分ずつ小袋に入れるなどの対策をしてください。
また、人の出入りが少ない場所や屋外にゴミ置き場がある場合は、ねずみなどが侵入する可能性があります。ねずみがゴミ袋を鋭い歯で食いちぎると、排泄物や食べカスなどが散らばってハエの発生につながるため、蓋付きのゴミ箱を使用するとよいでしょう。
今いるハエを駆除する方法
最後に、今いるハエを駆除する方法をご紹介いたします。まずは、ハエが発生した場所と原因を特定し、ハエのエサになっているものを撤去しましょう。エサは卵を産み付けられている可能性があるため、ゴミ袋に入れて口をしっかりと縛り処分してください。
飛んでいるハエの駆除は、殺虫剤の使用が最も効率的です。ただし、殺虫剤を使用する際は食品を片付け、化学物質に敏感な方やアレルギー症状の出る方、小さなお子さん、ご年配の方にも配慮しましょう。また、小動物や小鳥、昆虫、熱帯魚などは少量の殺虫剤成分で弱る可能性があるため、退避させてから使用し、ハエを駆除した後は換気を行ってください。
まとめ
今回は、ハエの生態と種類、ハエによる被害、ハエが発生しやすい場所と原因、ハエの予防と対策などについてご紹介しました。ハエは繁殖のスピードが早いだけでなく、一度に繁殖する数も多いため、住み着かれると非常に厄介な害虫です。
さまざまなハエからご自身やご家族を守るためにも、ハエの予防や対策に努めて見つけ次第駆除を行いましょう。また、近年では空調や床暖房などで住宅環境が良くなっているので、冬も油断できません。ゴミを放置しない、繁殖の環境をつくらないといった基本的な対策に加えて、殺虫剤の常備もおすすめします。








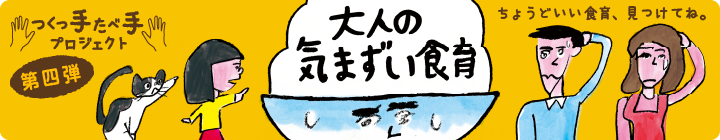
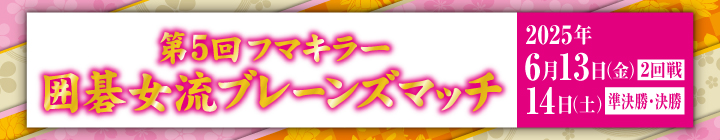

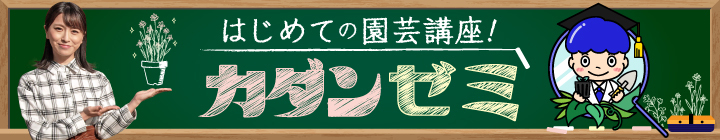
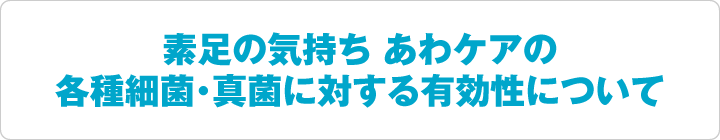
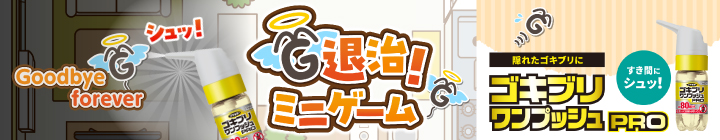
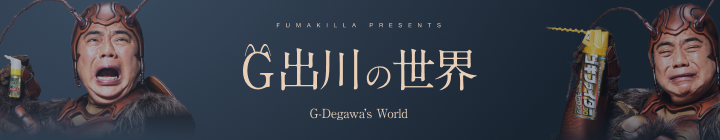






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



