2018年5月25日 | 虫
ムカデを見かける原因とは?ムカデの退治方法と予防対策

攻撃性が高く、強い毒性を持つムカデは身近にいる害虫の中でもおそろしい存在と言えます。咬まれるとかなり痛いため、トラウマになったという方もいるのではないでしょうか?
エサを求めて人家に侵入してくることもあるため、しっかりとした対策が必要です。
この記事ではムカデの生態や見かける原因などを紹介します。ムカデを退治する方法や寄せ付けない方法も解説するため、ぜひムカデ対策の参考にしてください。
ムカデとは?
漢字では「百足」と表記されるムカデは、多くの脚を持ち、その脚の数は種類によってさまざまです。ほとんどのムカデには毒があり、この毒を使って小動物や他の虫を捕食します。普段はじっとしていますが、捕食する際や天敵から逃げる際には素早く移動ができ、運動能力は非常に優れています。
戦国時代には、ムカデは後退できないことから「勝利」をつかさどる縁起の良い虫とされ、武家の家紋に使われていたと言われています。また、たくさんの脚があることから「脚が多い」が「おあし(お金)が多い」につながるとして「商売繫盛」のご利益があるとも考えられていました。
しかし、現代の日本においては、ムカデは危険な害虫とされています。攻撃力が強く、人に対する咬みつき被害も多く報告されています。
ムカデの生態
まずはムカデの生態や習性を知りましょう。ムカデについて知ることで対策や予防がしやすくなります。
ムカデの生息場所
日中は石やレンガ、落ち葉の下などでじっとしています。基本的に暗く、湿気の多い場所を好むようです。夜になるとエサを求めて人家に侵入することもあります。
ムカデの活動時期
ムカデは冬の間は冬眠しており、活動時期は春から秋にかけてです。特に産卵期とされる梅雨の時期には多く活動します。
ムカデのエサ
ムカデは肉食動物であり、ゴキブリなどの小さな昆虫を食べることがよく知られています。しかし、まれにネズミやコウモリなどの大型の動物も捕食することがあります。
ムカデの種類
世界では3,000種類を超えるムカデがいると言われています。日本にも100種類以上のムカデが生息しており、その中でもわたしたちの生活圏でよくみられるムカデを紹介します。
トビズムカデ
一般的に「オオムカデ」と称されるのがこのトビズムカデです。体長は8~15センチメートル程度で、大きいものでは20センチメートルを超えることもあります。
頭の部分が赤く、体は黒、足は赤やオレンジ色をしているものが多いですが、体色には個体差が見られます。
噛まれると激しい痛みを感じたり、噛まれた箇所が赤く腫れたりするため注意が必要です。
アオズムカデ
アオズムカデの体長は約10センチメートルですが、国内に生息するムカデの中では最も強い毒を保有していると言われています。頭と体は緑がかった黒、足はオレンジ色です。ただし、トビズムカデ同様、体色の個体差が大きい傾向にあります。
セスジアカムカデ
セスジアカムカデは体長5~6センチメートルで、体色は暗褐色です。北海道以南の日本各地に広く分布しています。
毒性はありますが、ほかの種類のムカデに比べると毒液が少なく咬まれてもそれほど痛みは感じません。
ムカデと似ている虫
ムカデとよく似ている虫も身近に存在するため、とっさに判断できないという方も多いようです。
以下の2種の虫は、身近に存在していてムカデとよく間違えられることがあります。いずれもムカデと違い積極的に人へ咬みつくことはありません。違いを知っておくと、いざというときに危険を回避できるでしょう。
ヤスデ
ムカデに比べてかなり小さく、日本で最も普通に見られるヤケヤスデの体長は18〜20ミリメートル程度です。移動する速度もムカデに比べると遅いのが大きな違いです。
また、ヤスデはひとつの節に2つ以上の脚が生えています。一方のムカデは、ひとつの節あたりの脚の数は1本です。
ムカデとは違い、ほとんど害のない虫とされていますが危険を察知すると刺激臭の強い体液を発します。むやみに触れるのはやめましょう。
ゲジ
「ゲジゲジ」とも言われるゲジは、ムカデより一回り小さく、体長より長い触角を持っていることが特徴です。生態や食性はほとんどムカデと変わりません。
毒も持っていますが積極的に人間を襲うことはほとんどなく、咬まれてもムカデほど被害がないことから益虫としての側面が大きいと言えます。
ムカデによる被害

ムカデは人への影響が大きく、咬まれるとただ痛いだけでは済みません。
ムカデの被害が私たちの健康や生活にどのような影響を与えるのかを具体的に確認し、対策に生かしましょう。
咬みつき被害
ほとんどのムカデには毒があります。ハチ同様、強い毒性を持ち、激しい痛みを伴います。また、アナフィラキシーショックを起こす可能性もあるため、生活圏で見かけた場合は十分注意が必要です。
ムカデは夜行性で暗いところを好むため、人が寝ている間に侵入してくることや靴の中に潜んでいることもあります。寝ている間や、出掛ける前に咬まれてしまうケースも多数報告されています。
咬まれた場合は流水できれいに洗い流し、抗ヒスタミン含有ステロイド軟膏を患部に塗るなどの処置を行い、念のため病院へ行きましょう。
不眠・精神的被害
一度咬まれた経験のある方や、部屋の中でムカデを見かけて駆除できなかった場合、咬まれるかもしれないという精神的恐怖が生じることがあります。特に寝ている間に咬まれるケースも多いため、眠れなくなる方も珍しくありません。
不快害虫としての被害
ムカデの見た目に生理的嫌悪感を覚える方も多いでしょう。脚がたくさんあり、毒々しい色をしているため見かけるとビックリします。見るだけでも嫌という方は多く、ネットの検索も怖くてできないという声もあるほどです。
ムカデをよく見かける原因

ムカデを見かける原因を知ることで、ムカデ対策・予防がしやすくなります。まずは原因を取り除くことから始めましょう。
ムカデのエサとなる害虫
日中、外にいるムカデがエサとなるゴキブリなどを求めて人家に侵入してくるケースがあります。自宅でムカデをよく見るという方は、ゴキブリをはじめとする害虫も潜んでいる可能性が高いです。
また、庭のメンテナンスや草刈りなどができていない場合もムカデのエサとなる他の虫を呼び込みやすくなります。庭の手入れの最中にムカデに咬まれたというケースもあります。
ムカデはつがい(夫婦)で行動する?
「ムカデは夫婦で行動する」という都市伝説やがありますが、特にそのような習性は確認されていません。単純にムカデを見かける環境下では他の個体も発見しやすいと考えられます。
ムカデの対策方法
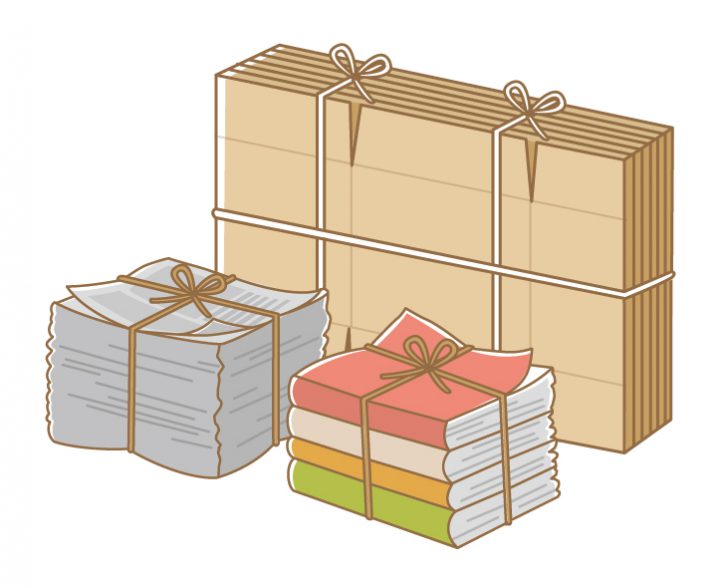
ムカデの生態、エサ、発生原因を知ったあとは具体的なムカデの対策方法を見ていきましょう。ムカデ被害は精神的にも衛生的にも影響が大きいです。しっかりと対策を行いましょう。
ムカデの予防方法と、実際に発見してしまった際の駆除方法をご紹介します。
ムカデの侵入を防ぐ
ムカデの活動が活発になる5月に入る前までに、ムカデが寄り付かないような対策を意識的に行うとより効果的です。
ムカデのエサとなる害虫対策を行う
メインとなるのはゴキブリなどの害虫を寄せ付けないことです。ゴキブリが住みやすい環境をつくらないように心がけましょう。ゴキブリは食べ残しだけではなく人の皮膚や皮脂などの有機物まで多くのものをエサとします。まずは室内を清掃し、清潔な環境を保ちましょう。
- 食べかす、ゴミはしっかり清掃・処分する
こまめに清掃を行って食べかすなどが床に落ちていないようすることは、ゴキブリ以外の害虫対策としても有効です。
ゴキブリやムカデの発見時期は他の虫の発見も多くなります。食物連鎖の関係で1種類の虫が活動すると、それを捕食する虫も活動します。ゴキブリとムカデの関係は代表的な例と言えるでしょう。
- 風通しを良くして湿気を除去する
ムカデ、ゴキブリをはじめとする多くの害虫は乾燥している場所を苦手とします。
- 侵入経路を塞ぐ
害虫は小さな隙間から侵入してきます。網戸の破損場や通気口、換気、住宅のひび割れや亀裂などをチェックし、隙間を塞ぐ対策を行いましょう。
- 段ボールなどを放置しない
段ボールにゴキブリが卵を産み付けることもあります。ムカデはゴキブリだけではなく、ゴキブリの卵もエサとします。長期間の放置は避け、なるべく早めに処分しましょう。
忌避剤を使用する
基本的な対策を行ったあとは、忌避剤を使ってムカデ対策を行いましょう。
住宅周りに撒く忌避剤や忌避効果のある殺虫剤スプレーなどがあります。注意すべきなのが、ムカデは住宅に侵入する害虫の中でも生命力が強いため、専用のものを使用する必要があるということです。
また、屋外でしか使用できないものもあるため使用上の注意をよく読んでください。
室内で使用する忌避剤はフマキラーの「お部屋の虫キラー1発ジェット」がおすすめ。侵入防止効果は最大2カ月、足で踏むだけなので簡単・安全に使用できます。ムカデ以外に100種類以上の害虫に高い駆除効果があります。
ムカデを駆除する
昔から言われるムカデの駆除方法として自力で捕獲し、熱湯に入れるというのがありますが、これは咬まれる危険性も高いです。ムカデは動きも早いため、自力で捕まえようとするとすぐに逃げられてしまうことも考えられます。
最も簡単でおすすめなのは、殺虫剤の使用です。
ムカデは神経節が節ごとにあるため、体を切断されてもしばらくは生きているということもあります。すぐに駆除できるように、ムカデ専用の殺虫剤を使用しましょう。
「ムカデフマキラー」は、歩行不能成分と冷却効果でムカデをすばやく駆除。最大1ヵ月間侵入を予防する効果もあります。
まとめ
ムカデは見た目もインパクトがあり、咬まれると痛いうえに毒で腫れてしまうこともあります。まずはエサとなる害虫の対策を講じ、忌避剤・殺虫剤を用いての予防をおすすめします。
対策は、ムカデをはじめとする害虫の活動が活発になる前に行うのが最も効果的です。早期対策でご自身や大切な家族を守り、快適な生活を送りましょう。








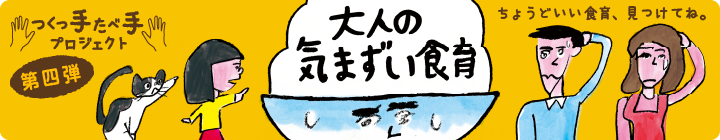
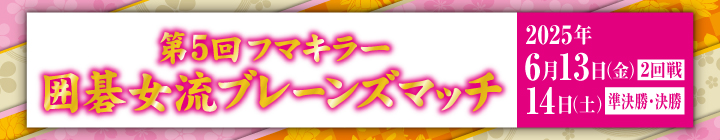

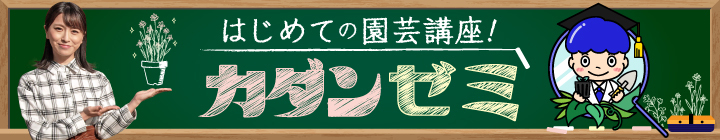
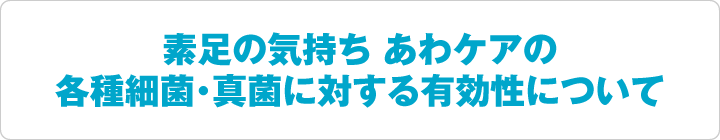
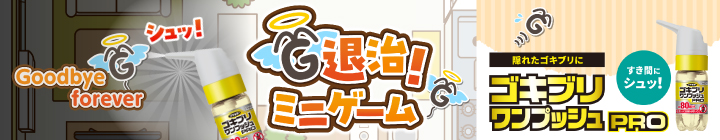
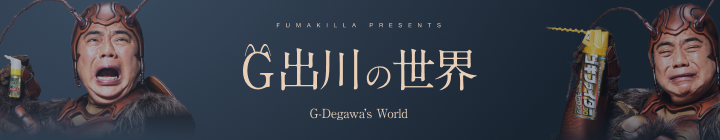






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



