2025年7月1日 | お役立ち情報
広島県竹原市はどんな町?魅力やグルメ、観光スポットを紹介

広島県竹原市は、瀬戸内海に面した自然豊かな町です。平安時代には、京都・下賀茂神社の荘園として栄えました。江戸時代に入ると製塩業や酒造業で大きく発展し、今もその面影を色濃く残す町並みは「安芸の小京都」と呼ばれています。
この記事では、竹原市の観光スポットや地元の人々に愛されるグルメについて、詳しくご紹介します。
竹原市の概要
竹原市は広島県沿岸部のほぼ中央に位置する人口約2万2千人(令和7年3月末時点)の市です。古くは平安時代に京都・下鴨神社の荘園として栄えた歴史を持ちます。その後、江戸時代には製塩・酒造業で大きく発展しました。製塩業で財を築いた豪商たちは「浜旦那(はまだんな)」と呼ばれ、街づくりや文化の発展に寄与しました。彼らが建てた邸宅は今も町並みを形成し、当時の繁栄を物語っています。
現在はそれらの建物を含む町並みがそのままに保存され、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。
竹原市の観光スポット
竹原市には、歴史を感じる町並みから自然を満喫できる島まで、魅力的な観光スポットが数多くあります。その中でも特におすすめのスポットを厳選してご紹介します。
町並み保存地区
竹原市観光の中心となるのが、江戸時代後期の雰囲気を残す「町並み保存地区」です。白壁の土蔵や格子窓を持つ屋敷が連なり、歩くだけで江戸時代にタイムスリップしたような気分を味わえます。落ち着いた風情が漂う町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。
竹原市はNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」のモデルとなったニッカウヰスキーの創業者・竹鶴政孝の故郷です。生家の竹鶴酒造は町並み保存地区にあり、ドラマのロケ地としても使われました。また、人気アニメ「たまゆら」の舞台でもあるため、作品のファンが「聖地巡礼」で訪れることも多く、観光客でにぎわいます。
竹原の歴史や文化をより深く知りたい方は、観光ガイドによる案内付きの散策もおすすめです。所要時90〜120分ほどの散策で、地元の観光ガイドが案内してくれます。申込先は「道の駅たけはら」内のたけはら観光ガイド会で、2か月〜3日前までに予約が必要です。
- 住所:広島県竹原市本町三丁目 ほか
- 参考URL:https://www.takeharakankou.jp/spot/4305
大久野島(おおおくのしま)

竹原市の忠海港から船で約15分の「大久野島」は、通称「うさぎ島」と呼ばれる人気の観光地です。近年は「ラビットアイランド」と呼ばれ、世界的にも注目を集めています。周囲約4キロメートルの小さな島ですが、500〜600羽ものうさぎが生息しており、餌をあげたり触れ合ったりと、癒やしのひとときを過ごせる島です。
また、島で唯一の宿泊施設「休暇村大久野島」では、天然ラドン温泉や瀬戸内の旬の食材を使った料理を味わえるほか、サイクリングや釣り、キャンプなどのレジャーも楽しめます。
一方で、大久野島はかつて毒ガス製造工場があったという歴史があり、毒ガスの製造過程で多くの方が犠牲になりました。その悲惨な過去を今に伝える施設として、1988年に大久野島毒ガス資料館が開館し、平和学習の場として多くの方が訪れています。
- 住所:広島県竹原市忠海町大久野島
- 参考サイト:https://www.takeharakankou.jp/spot/4304
西方寺 普明閣(さいほうじ・ふめいかく)
西方寺は、町並み保存地区の高台に建つ浄土宗のお寺です。かつては禅寺の妙法寺がありましたが、1602年の火災で焼失。翌年、西方寺が同じ場所に移り、宗派も浄土宗へと改宗されました。
本堂の横にある普明閣は1758年に建てられ、京都の清水寺を模しているといわれています。妙法寺時代のご本尊であった木造十一面観音立像(県重要文化財)を祀る建物として再建されました。建築は方三間宝形造で本瓦葺の二重屋根、舞台作りとなっています。
舞台からは、瓦屋根が連なる町並み保存地区を一望できるため、竹原を訪れる人にとっては必見のスポットです。
- 住所:広島県竹原市本町3-10-44
- 参考サイト:https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkashogaigakushuka/gyomuannai/9/1/10/2429.html
旧松坂家住宅
町並み保存地区の「旧松坂家住宅」は、製塩や酒造業で栄えた豪商の邸宅で、市の重要文化財に指定されています。江戸時代末期に建てられ、明治12年に全面改築されました。波打つような曲線を描く唐破風の屋根や、菱格子の出窓など、華やかな建築意匠が特徴です。内部は数寄屋風の造りになっています。
- 住所:広島県竹原市本町3-9-22
- 参考サイト:https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkashogaigakushuka/gyomuannai/9/1/10/2437.html
胡堂(えびすどう)

本町通りの北側に位置する胡堂は、竹原の小祠の中でも最古で最大規模を誇ります。製塩業が盛んだった時代、この地区は上市・下市と呼ばれ、胡堂は上市の商業の守り神として祀られていました。
現在も商業の繁栄を願って毎年10月に祭礼が行われます。大林宣彦監督の映画「時をかける少女」のロケ地としても有名です。
- 住所:広島県竹原市本町3丁目
- 参考URL:https://www.takeharakankou.jp/spot/4322
まちなみ竹工房
竹原市は竹細工が特産品です。まちなみ竹工房は町並み保存地区の本町通り沿いにあり、予約不要で竹細工体験ができるスポットです。職人の指導を受けながら、竹かごや竹とんぼなどの竹細工を制作できます。
制作時間は40分〜1時間ほどなので、観光の合間にも気軽に参加でき、旅の思い出作りにぴったりでしょう。工房内では職人が制作した竹製品の展示販売も行われています。
- 住所:広島県竹原市本町3-12-14
- 参考サイト:https://www.takeharakankou.jp/spot/4328
竹原市歴史民俗資料館

「竹原市歴史民俗資料館」は、竹原の歴史を知りたい方におすすめの施設です。昭和初期に町の図書館として建てられた洋風のモダンな建物を活用しています。もともと江戸時代中期の儒学者・塩谷道碩の旧宅跡で、頼山陽の叔父・春風が志を受け継いで学問所にしていました。館内では、竹原が製塩業で栄えた歴史を中心に、貴重な資料が展示されています。
- 住所:広島県竹原市本町3-11-16
- 参考サイト:https://www.takeharakankou.jp/spot/4327
ピースリーホーム バンブー総合公園
竹原市の町づくりのシンボル「竹」をテーマにした総合公園です。園内にはさまざまな文化施設やスポーツ施設があり、自然や文化、運動を楽しめます。
竹の館には竹の生態を学べる展示室や工芸教室があり、和室(茶室)も備えています。屋外には海の展望台や山の展望台、多目的グラウンドや芝生広場、子ども用の総合遊具などがあり、子どもと一緒に楽しく遊べるでしょう。公園内には約20種類・1,300本もの桜の木があるため、春には花見も楽しめます。
- 住所:広島県竹原市高崎町1414
- 参考URL:https://www.takeharakankou.jp/spot/4333
竹原市のおすすめグルメ

旅の楽しみといえば、やはり外せないのがご当地グルメです。製塩と酒造で栄えた竹原市には、歴史や風土を感じられる料理が受け継がれています。竹原を訪れたらぜひ味わってほしいグルメをご紹介します。
純米吟醸たけはら焼き
広島県は地域ごとに個性豊かなお好み焼きがあります。竹原市のご当地お好み焼きは「純米吟醸たけはら焼き」です。酒造りが盛んな竹原らしく、生地には市内3つの酒造で作られる酒粕が練り込まれています。酒粕のほんのりした香りと自然な甘みが特徴です。市内の「御幸」「ほり川」など、6店舗で提供しているので、食べ比べをするのも楽しいでしょう。
魚飯(ぎょはん)
竹原市の郷土料理「魚飯(ぎょはん)」は、「幻の郷土料理」とも呼ばれます。江戸時代、製塩業で栄えていたころ、塩田を所有して莫大な富を築いた「浜旦那」と呼ばれる豪商たちが、お客様をもてなすために振る舞ったと伝えられています。竹原の繁栄を象徴するごちそうです。
魚飯は手間がかかる料理です。新鮮な鯛やカレイなどの白身魚を焼いて丁寧にほぐし、えびや椎茸、筍など彩り豊かな具材と合わせます。その上から旨みのきいただし汁を注ぎます。具材は細かく切り、出汁は2度とるなど、下ごしらえに手間をかけた魚飯は、単においしい料理を提供するというだけでなく、おもてなしの気持ちがこもっているのが特徴です。
1960年頃、塩田は国策で廃止され、魚飯を作る機会も次第に減少しました。現在では町並み保存地区の商家に伝承されるのみで、「幻の郷土料理」と呼ばれています。それでも一部の飲食店で魚飯を提供しているため、観光で竹原を訪れた際に味わえます。
日本酒
竹原市は古くから酒造りが盛んです。日照時間が長く、降雨量が少ない竹原は、塩田に適していると同時に米作りにも適しており、その環境を生かして全盛期には26件の造り酒屋がありました。現在も「竹鶴酒造」「藤井酒造」「中尾醸造」という3つの酒蔵があります。
藤井酒造は酒蔵の一角を交流スペースとして改装し、「龍勢」や「夜の帝王」など、数種類のお酒を試飲できるコーナーが用意されています。試飲は無料で、気に入った一本が見つかれば、その場で購入可能です。
まとめ
「安芸の小京都」と呼ばれる広島県竹原市は、江戸時代の風情が残る美しい町並みと、瀬戸内海の穏やかな自然が調和した魅力あふれる場所です。歴史的な建造物が並ぶ町並み保存地区を散策したり、うさぎと触れ合える大久野島で癒されたりなど、さまざまな楽しみ方ができます。また、酒粕を使った「たけはら焼き」や幻の郷土料理「魚飯」など竹原ならではのグルメも魅力です。
次の旅行先を探している方は、広島県竹原市を候補に加えてみてはいかがでしょうか。歴史と自然、グルメがそろう竹原市は、きっと心に残る旅になるでしょう。








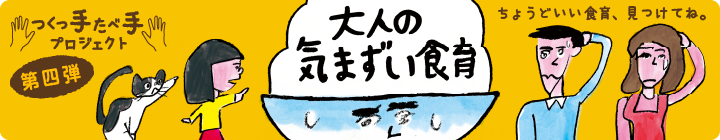
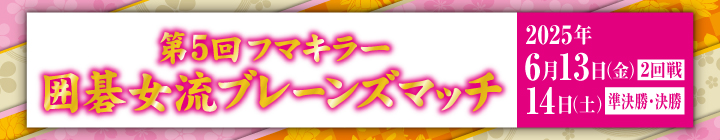

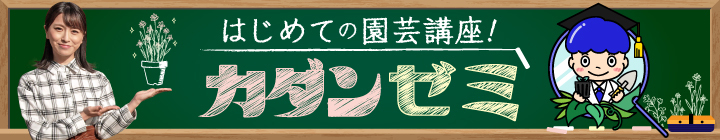
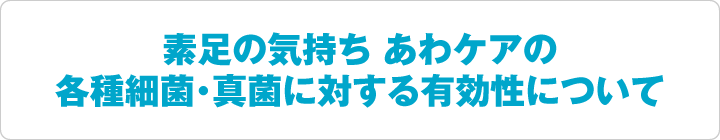
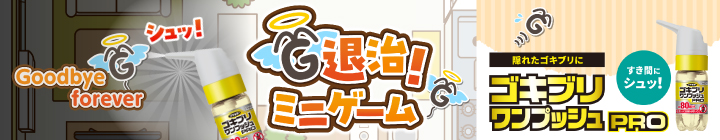
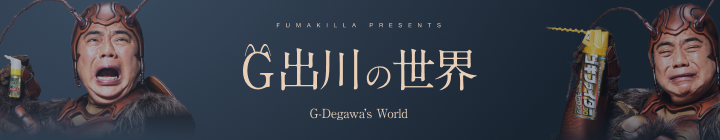






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



