2018年3月15日 | 虫
クモ(蜘蛛)が発生する原因とは?クモの習性を知って対策しよう

独特な形状や捕食する様子、網を張る習性などから敬遠されがちなクモですが、実は、生活に役立つ「益虫」として知られています。一部のクモを除いて、人に無害な生き物です。ただし、住宅内でクモをよく見かける場合は、エサになる害虫が潜んでいる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、クモの生態や主な種類、クモによる被害、クモが発生しやすい場所と原因、クモの予防と対策などについてご紹介します。住宅の管理にぜひ、お役立てください。
クモの生態と種類について

はじめに、クモの生態と主な種類についてご紹介します。
クモの生態
クモは節足動物の仲間で、触覚を持たず、体が2つの部分(頭胸部と腹部)に分かれ、8本の足を持つ点で、ハエやアリなどの昆虫とは異なります。昆虫は体が頭部、胸部、腹部の3つに分かれ、6本の足を持つため、明確に区別されます。世界には、およそ50,000類のクモが確認されており、国内ではおよそ1,700種類が生息している とされています。
クモは、その生態によって大きく2つのタイプに分けることが可能です。
- 徘徊性:網を張らずに動き回りながら獲物を捕らえるタイプ
- 造網性:クモの網を張り、そこに獲物を捕らえるタイプ
日本に生息するクモの多くは、ハエやゴキブリ、蚊、ガなどの害虫を捕食するため、益虫として知られています。
身近なクモの種類
私たちの身近でよく見かけるクモは、次のとおりです。
ハエトリグモ
ハエトリグモは、跳躍力に優れた徘徊型のクモで、海外では「ジャンピングスパイダー」とも呼ばれるほどの運動能力を持っています。複数の目と発達した視力を持ち、体長は8ミリ前後のものが多く足は短めです。名前のとおり、ハエ類を含む小型の昆虫を捕食します。
ハエについては、「ハエ(蠅)が発生する原因とは?ハエの習性を知って対策しよう」の記事で詳しくご紹介しています。
アシダカグモ
アシダカグモは、体長が20~30ミリ前後の徘徊性のクモで、ゴキブリなどの昆虫類を主食にしています。大きくて足が長く、迫力がある見た目に特徴があります。メスは円盤形の卵を抱え、幼体が出てくる直前まで持ち歩きます。
ゴキブリについては、「ゴキブリが発生する原因とは?習性を知って対策しよう」の記事をご覧ください。
ジョロウグモ
ジョロウグモは、黄色と青のカラーリングで、楕円(だえん)型の胴体を持つ造網性のクモです。夏から秋にかけて、細かい網目(あみめ)の網を張ります。ジョロウグモは、メスがおよそ20~30ミリと大型なのに対して、オスはその半分程度です。
コガネグモ
コガネグモは黄色と黒のカラーリングと、足の太さに特徴がある造網性のクモです。ジョロウグモと混同されやすいクモですが、カラーリングと足の特徴で判別できます。網にX字型やその一部を省略した隠れ帯を付けます。コガネグモのメスはおよそ20~30ミリ、オスはおよそ6ミリです。
【毒グモ】セアカゴケグモ
セアカゴケグモは、日本で警戒が必要な毒グモの一種で、特定外来生物に指定されています。本来はオーストラリア原産のクモですが、1995年に大阪府で発見され、その後全国的に分布が広がりました。各自治体のホームページなどでも注意を呼びかけています。
セアカゴケグモは、丸い腹部の腹側に赤いひし形が縦に2つ並んだ砂時計模様が特徴です。セアカゴケグモは公園などの人工物が多い場所にいることが多いため、小さなお子さんは十分に注意してください。
セアカゴケグモについては「【特定外来生物】セアカゴケグモの生態・被害・対策について」でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
クモによる被害について

クモによる被害は、クモの外見やクモの網が与える心理的な被害と、刺咬による被害が挙げられます。
不快感・不潔感
クモの見た目や捕食する姿、徘徊する様子などに不快感を抱く人が少なくありません。また、クモの網が急に顔や服などに付いたときは、多くの人が嫌な気分になるでしょう。クモの網が張り巡らされた部屋は、清潔感が失われて生活に支障をきたします。
住宅の外側や庭にクモの網がある場合は、景観を損ねるだけでなく、近隣に迷惑をかけることもあります。
毒グモによる健康被害
先述したセアカゴケグモは、神経毒を持っています。人を攻撃することはないので直接触れない限り咬(か)まれる心配はありません。しかし、近くにいることに気付かず、誤って触れたり踏んだりして咬まれたという事例はいくつも報告されています。
セアカゴケグモに咬まれたときは、痛みやしびれ、発熱、頭痛などの症状が出ることがあります。毒はそれほど強くないため、国内では重篤(じゅうとく)な症状は報告されていませんが、咬まれた場合はすぐに医療機関に相談してください。
クモ・クモの網が発生する場所と原因

続いて、クモとクモの網が発生しやすい場所と原因についてご紹介します。
クモが発生しやすい場所
クモが発生しやすい場所は、エサになる害虫がいると考えましょう。クモが好むエサは、ハエやコバエ、ゴキブリ、蚊などです。これらの害虫が好むエサは、主に残飯や野菜くず、お菓子の食べこぼしなどであるため、キッチンやリビングなどが該当します。上記の害虫は水分補給のため、洗面所やバスルームなど水回りにも出没します。玄関やベランダのある部屋でも人と一緒に出入りしている可能性が高いでしょう。また、ハエは食物だけでなく排泄物から蛋白(たんぱく)質を摂取するため、トイレにクモが発生することも少なくありません。
クモが網を張りやすい場所
造網性のクモは、お尻から糸を出して室内や屋外のさまざまな場所に網を張ります。クモが網を張りやすい条件は、
- エサになる虫が集まる場所
- 雨や風に当たりにくい場所
- 網を張る足場がある場所
などが挙げられます。
したがって、室内でクモが網を張りやすい場所は天井の角など、屋外では樹木の枝、街灯の下、軒下(のきした)などが該当します。セアカゴケグモは、主に公園のベンチの下やガードレールの柱、側溝(そっこう)のふたの下などに網を張ります。
クモ・クモの網の予防と対策

次に、クモとクモの網の予防と対策についてご紹介いたします。
まずは害虫の対策から
クモをよく見かける・駆除しても室内に入ってくる場合は、室内にハエやゴキブリといった害虫がいる可能性が高いと考えましょう。これらの害虫は、不快な気持ちにさせるだけでなく、感染症を引き起こす病原体を運ぶ可能性があるため、生活上の衛生面や健康面の被害が心配されます。
したがって、まずは害虫の発生を防ぐことが根本的な解決につながります。具体的には、次のような方法をおすすめします。
ハエ・コバエ対策
ハエやコバエは、腐敗した野菜や果物、排泄物などをエサにしています。こまめにキッチンの掃除に取り組み、生ゴミはビニール袋で密封してふた付きのゴミ箱に捨ててください。また、熟すと匂いが強くなるバナナなどを室内に放置しないようにしましょう。トイレはニオイがこもりやすいので、定期的な掃除と換気を心がけてください。
ゴキブリ対策
ゴキブリは、残飯だけでなく、人間の皮脂や髪の毛、爪などの蛋白源、コーンスターチを含む段ボールなどをエサにしています。室内の清潔を保ち、ゴミや段ボールを放置しないようにしましょう。さらに、ゴキブリが侵入しやすい壁や窓などのすき間をふさぐ、ゴキブリが潜むスペースをつくらないなどの対策も必要です。
クモの対策
害虫の対策と並行して、クモの対策にも取り組みましょう。クモの侵入は、市販の忌避剤(きひざい)で予防できます。忌避剤はスプレーやテープなどのタイプがあるので、使いやすいものを選んでください。
クモの網の対策
天井の角や街灯の下などに張られやすいクモの網は、あらかじめ忌避剤やハッカ油スプレーを散布することで防げます。スプレーの効果が持続する期間は商品によって異なるので、使い方に従って適切に散布しましょう。
フマキラーの「クモの巣ゼロバリアスプレー」は、気になる場所にスプレーしておくだけで、最大2ヵ月(※)巣を張らせません。雨や日光にも強く、屋外でもしっかりと効き目が持続します。また殺虫効果もありますので、クモを見かけたらすばやく退治できます。
(※)降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。
クモの駆除・クモの網を除去する方法
最後に、クモの駆除とクモの網を除去する方法についてご紹介します。
クモの駆除
室内でクモを見つけたときは、ティッシュペーパーやビニール袋などを使用して捕まえたり、紙の上に乗せたりして外に逃がしましょう。触ることに抵抗がある場合は、クモ用の殺虫剤を使用して処分してください。セアカゴケグモを見つけた場合、判断が難しい場合は、自治体に連絡してから対処しましょう。
クモの網の除去
クモの巣は、新聞紙や三角コーナー用のネットなどを巻いたほうきや長い棒を使うか、掃除機で吸うなどして取り除いてください。クモの巣があった場所は再び巣を張られる可能性が高いので、アフターケアとして忌避剤をスプレーして予防しましょう。
屋外の場合は、雨などで薬剤が流されて効果が薄れやすいため、定期的に忌避剤をスプレーしてください。
まとめ
今回は、クモの概要とクモによる被害、クモが発生しやすい場所と原因、クモの予防と対策などについてご紹介しました。クモは一部を除いて人に害を与えない益虫ですが、室内でクモをよく見かける場合は、エサになるハエやゴキブリなどの害虫が潜んでいると考えましょう。
クモの対策は、エサになる害虫の駆除と忌避剤の導入をおすすめします。








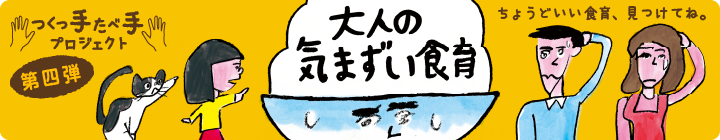
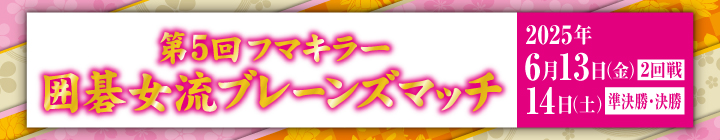

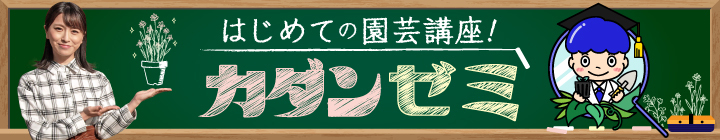
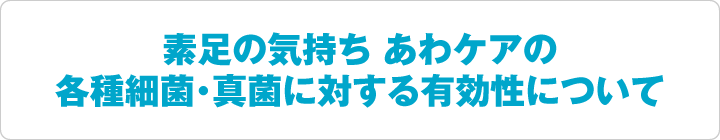
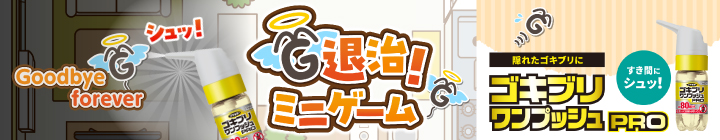
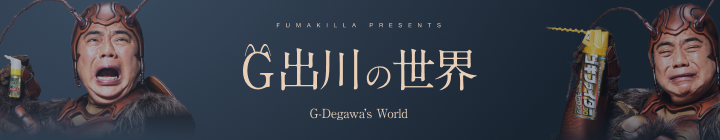






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



