2025年3月4日 | お役立ち情報
広島県で取れる山の幸は?おすすめの郷土料理を紹介

広島県はカキをはじめとした海の幸が豊富で、自然豊かな土地であるため山の幸も豊富です。しかし、広島の山の幸にどのようなグルメがあるか、知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、広島県の山の幸をご紹介します。山の幸を使ったおすすめの郷土料理やご当地グルメも紹介するので、広島を訪れたときは、ぜひ味わってください。
広島県の山の幸
広島県の北部には中国山地があるため、自然の中で育まれた山の幸が豊富です。まずは、広島県の代表的な山の幸をご紹介します。
こんにゃく
庄原市総領町は、こんにゃく芋の日本有数の産地です。中国山地の谷間に位置する総領町は、春になると雪解け水が流れ込み、清らかな水と澄んだ空気に恵まれています。この風土を生かし、独自の製法によって、総領こんにゃくは独特の風味と食感を生み出します。
総領こんにゃくは、昔ながらの生芋からの製造にこだわっていることが特徴です。日本に古くから伝わる「在来種」という芋を使用し、100年以上前から伝わる昔ながらの製法で作られています。
松きのこ・松なめこ

松きのこ・松なめこは、日本有数の松茸の産地であった世羅町の世羅きのこ園で、約20年の歳月をかけて作られたシイタケの一種です。
松きのこは、傘は肉厚でジューシーであり、軸は太く締まってシャキシャキとした歯ごたえを楽しめます。ほんのりした甘さと自然のキノコに似た芳醇な香りが特徴です。栄養面ではビタミンやβグルカンが豊富です。
松なめこも松きのこと同様にビタミンやβグルカンを豊富に含んでいます。松なめは、一般的ななめこに比べてかなり大きいことが特徴です。市販のなめこに比べると10〜20倍の大きさです。なめこ特有のぬめりも少ないため、洗わずそのまま調理できます。フライパンで軽く乾煎りすると、芳醇な香りとシャキシャキした食感が楽しめます。
トマト
広島県の芸北地区は、標高600メートルに位置します。昼と夜の温度差が10℃以上ある高冷地特有の気候で作られる芸北トマトは、色鮮やかです。このトマトは「桃太郎」品種の中でも実が大きく、甘みが強くて熟しても果肉が崩れにくいことが特徴です。芸北地区は雨の多い地域ですが、昭和49年の雨除け栽培技術導入によって、トマトの品質が向上しました。
タラの芽
広島市佐伯区湯来町では、1995年から「山菜の王様」と呼ばれるタラの芽を生産しています。寒冷の休耕田を利用した良好な栽培技術によって「湯来町のタラの芽」というブランドを確立しています。出荷時期は1月~4月上旬です。ほろ苦さと香りが春の訪れを感じさせるタラの芽は、天ぷらにして食べるのが一般的です。
じゃがいも
東広島市南部に位置する安芸津町は、じゃがいもの栽培が盛んです。安芸津町木谷の赤崎地区を中心に明治末期から栽培が始まりました。瀬戸内海に面する安芸津町は年間を通して温暖な気候で、海風や太陽を浴びる傾斜のある地形、水持ちと水はけの両方に優れた赤土の土壌というじゃがいもの栽培に適した条件がそろっています。安芸津町のじゃがいもは、ホクホクした食感と甘みが魅力です。
「マル赤」の名称で知られるマル赤馬鈴薯は、春と秋の年に2回出荷されます。特に秋のじゃがいもは味が良いといわれています。品種は出島が80%以上で、肉色は黄色、肉質はみずみずしいのが特徴です。じゃがバターやコロッケにして食べると、ホクホク感や甘みを感じられます。
ほうれん草
山間部の北広島町や庄原市などは、ほうれん草の栽培が盛んです。標高1,000m以上の山々が連なる北広島町は、冬季は積雪量が多く、夏は冷涼な気候です。中国地方を代表する江の川と太田川水系の源流域でもあります。このような地勢を生かし、冷涼な気候を好むほうれん草の栽培が盛んです。
広島県の北東部に位置する庄原市は西日本有数の豪雪地帯であり、昼夜の寒暖差が大きいため、ほうれん草の栽培が盛んです。庄原市西城町では、冬季限定で「寒じめほうれんそう」が出荷されます。寒じめとは、ほうれん草が強い寒さから身を守るために糖度を高める特性を持つことを利用した栽培方法です。
ハウスの側面を開けて冷たい空気に触れさせると、葉が肉厚になって甘さが増します。町の特産である「ヒバゴンネギ」の後作として、ハウスが有効活用されています。
ヒバゴンネギ
庄原市西城町では夏でも涼しい気候を生かし、青ネギの栽培も盛んです。ヒバゴンとは、庄原市西城町の比婆山麓でゴリラに似た体つきの謎の類人猿が目撃され、出没地にちなみ「ヒバゴン」と名づられたことに由来します。出没から数年後には目撃情報が途絶えましたが、西条町のキャラクターとなっています。町のキャラクターにちなみ、「ヒバゴンネギ」と名づけられました。
吉和わさび
宮島の厳島神社が有名な廿日市市は、瀬戸内海から中国山地まで南北に長く広がっているため、海の幸も山の幸も楽しめる地域です。山間部の吉和は、山々から流れ落ちる雪解け水が清流となり、その恵みをうけておいしいわさびが育ちます。特に吉和のわさびを漬け込んだわさび漬けなどが有名です。
ルバーブ

廿日市市吉和の特産品となっているのが、ルバーブです。ルバーブとはシベリア原産のタデ科の多年草で、赤い茎と甘酸っぱい味が特徴です。ジャムなどの加工品も販売されています。
ルバーブは食物繊維などの栄養が豊富で、ヨーロッパではポピュラーな食材ですが、日本での栽培はほとんどありません。冷涼な気候での栽培が適しているため、吉和地域は日本最南端の栽培地です。
比婆牛
比婆牛(ひばぎゅう)は、庄原市内で生まれた肉質等級3級以上のブランド牛で、広島和牛の一つです。広島県北東部に位置する庄原市は、標高150〜200メートルの盆地を中心に緩やかな起伏の地形が広がり、中国山地特有の冷涼な気候に恵まれています。比婆牛は生産数が少なく、そのほとんどが地元で消費されるため、市場にはめったに出回りません。希少価値の高い幻の和牛と呼ばれています。
比婆牛の特徴は、くちどけの良さです。赤みに細かく入る網目状の「小ザシ」と呼ばれる脂肪「小ザシ」が、比婆牛は多いといわれています。
広島県の山の幸を使った郷土料理・ご当地グルメ
続いて、広島県の山の幸を使った郷土料理やご当地グルメをご紹介します。
山ふぐ

山ふぐは、広島市佐伯区湯来町の郷土料理です。名前に「ふぐ」とありますが、魚のふぐではなく、こんにゃく料理です。薄切りにしたこんにゃくを刺身のようにして食べると見た目がふぐに似ていることから「山ふぐ」と名づけられました。
八寸
八寸とは、山の幸と海の幸を組み合わせて作った煮物で、熊野町や安芸高田市など安芸門徒の多い地域で食べられてきた郷土料理です。安芸門徒とは、広島県西部地方に多い浄土真宗門徒を指します。
八寸という名前は、料理を盛り付ける漆器の直径が八寸(約24センチ)であることに由来するという説があります。
八寸は、魚の「あら」と自宅で作った野菜を煮込んだのが始まりで、正月や冠婚葬祭など人が集まる場で作られること多い料理です。食材は魚のあらの他に鶏肉、里芋、れんこん、人参、大根、ごぼう、しいたけなどが使用されます。
お祝いの席では、具の種類を奇数にし、朱色の器に盛るのが一般的です。一方、葬式や法事では、具材の種類を偶数にし、黒の器を用います。この際、動物性の食材は使わずに、厚揚げや油揚げで代用するなど、地域によって決まりがあります。
懐石料理にも「八寸」という料理がありますが、広島の八寸と同じものではありません。
煮ごめ
煮ごめとは、安芸門徒が多い県西部地域を中心に食べられてきた郷土料理で、親鸞聖人の命日前後の「御逮夜(おたんや)」に食べる精進料理です。
小豆や大根、にんじん、ごぼう、れんこん、里芋、干しシイタケ、油揚げ、こんにゃくなどをさいの目に切って煮込んだもので、山の幸がたっぷり使われています。精進料理のため、出汁や肉、魚は使いません。
親鸞聖人の命日である1月16日を「御正忌」といい、前夜から当日までが「御逮夜(おたんや)」とされています。煮ごめは御逮夜の前日にたくさん作り、3日間にわたって煮返しながら食べたといわれています。その由来は、親鸞聖人が重体のときに弟子たちが暖を取るため、野菜と親鸞聖人の好物である小豆を煮込んで食べたことにあるとされています。
「御逮夜」の時期は殺生を避ける風習があり、漁業者は漁を休み、魚市場も3日間閉まっていたことから「おたんやの市止まり」と呼ばれていました。しかし、現在では「おたんやの市止まり」の風習は廃れ「御逮夜」の期間に煮ごめを食べる習慣も減りつつあります。
ジビエ料理
広島市佐伯区湯来町は、7割以上が森林におおわれた自然豊かな地域です。この湯来町の山を駆け回ったイノシシは運動量が多く、自然の恵みを食べて育っているため、肉質が優れていることが特徴です。湯来町には、湯来ジビエのイノシシ肉を使ったジビエ料理やぼたん鍋が味わえる店が複数あります。
湯来ジビエは良質なイノシシを提供するために、湯来町伏谷にある食肉処理施設から概ね1時間の距離で捕獲したイノシシ限定と定義されています。また、湯来ジビエは湯来ジビエの会のメンバーのみで捕獲・処理したイノシシしか扱っていません。
ウニホーレン

「ウニホーレン」は、海の幸と山の幸を使った広島のご当地グルメです。茹でたほうれん草をバターとしょうゆで炒め、その上にウニをたっぷり乗せた料理です。テレビ番組で紹介されたことをきっかけに、全国的に有名になりました。また、広島には「ウニクレソン」というご当地グルメもあります。ほうれん草の代わりにクレソンを使った料理で、作り方はウニホーレンと同じです。
まとめ
広島県といえばカキやアナゴ、小イワシなど海の幸を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、山の幸も豊富です。野菜やキノコ、ジビエ料理や比婆牛など、広島の山の恵みを味わってみませんか?
海の幸と山の幸を同時に味わえる料理も多いため、広島県を訪れたときは、ここでしか味わえないグルメを堪能してください。








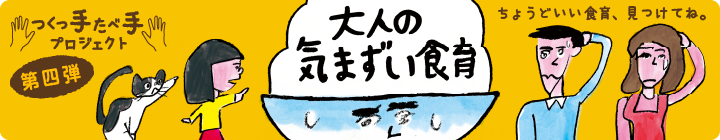
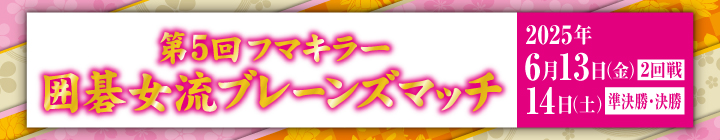

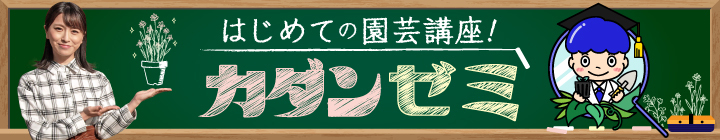
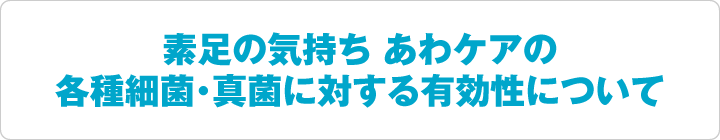
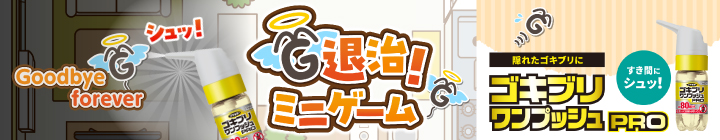
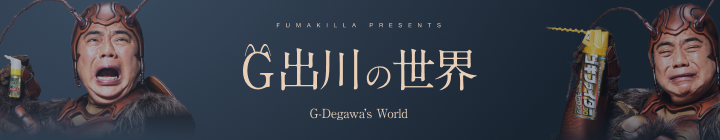






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



