2025年6月2日 | お役立ち情報
広島県で有名な野菜は?7大葉物野菜を紹介

自然豊かで温暖な気候の広島県では、年間を通してさまざまな野菜が生産されています。特にレモンやネーブルなどの柑橘類の名産地として知られていますが、葉物野菜の生産も盛んです。また、ねぎに似た「わけぎ」や、お正月料理に欠かせない「くわい」は、広島県が日本一の生産量を誇ります。
本記事では、広島県で生産量の多い代表的な野菜や、広島市が特に力を入れている「広島近郊7大葉物野菜」、広島で受け継がれてきた伝統野菜の魅力についてご紹介します。
広島で生産量が多い野菜
広島県を代表する生産量の多い野菜について、特徴や栽培地域、旬の時期などをご紹介します。
わけぎ
広島県は、わけぎの生産量が全国一です。わけぎは、ねぎと玉ねぎの雑種であり、種子ではなく「種球」という球根を植えて育てます。成長するといくつもの株に分かれて増えることが「わけぎ(分葱)」の名前の由来であり、子孫繁栄を象徴する縁起物とされています。
広島の温暖な気候で育つ広島わけぎは、香りや甘味が特長です。香りがマイルドで辛みが控えめなため、ねぎ特有の強い香りや刺激が苦手な方でも食べやすいでしょう。主に尾道市や三原市の沿岸部で栽培され、9月〜4月頃に出回ります。
くわい

広島県福山市はくわいの産地で、全国一の生産量を誇ります。くわいは水田で育てられる水生多年草で、ほっこりした食感とほろ苦さが特長です。明治時代に沼地に自生していたものを福山城の堀に植えたのが栽培の始まりといわれています。実からしっかりした芽が出る様子が「芽出たい(めでたい)」と連想され、成長や繁栄を象徴し、縁起物として正月料理に欠かせません。そのため、ほとんどが年末に出荷されます。
福山市で栽培されているのは「青くわい」という種類です。外皮がツヤのある鮮やかな藍色をしていることから「田んぼのサファイア」とも呼ばれています。
ばれいしょ
東広島市の安芸津町や三原市、竹原市は、ばれいしょ(じゃがいも)の有名な産地です。特に安芸津町赤崎地区は、傾斜地の水はけのよい赤土がばれいしょの栽培に適しており、東広島を代表する農作物「安芸津マル赤馬鈴しょ」が生産されています。出荷時期は6月〜9月、12月〜2月で、7月と12月に最盛期を迎えます。
アスパラガス
広島県内ではアスパラガスの栽培も盛んで、露地栽培が行われています。アスパラガスはハウス栽培が多いですが、広島のアスパラガスは太陽の光をたっぷり浴びて育つため、濃い緑色をしているのが特長です。アスパラガスは疲労回復効果があるといわれるアスパラギン酸を含み、栄養ドリンクにも使用されています。東広島市、世羅町、三原市、福山市、安芸高田市、三次市、庄原市などで栽培され、3月〜10月に出荷されます。特に5月・7月頃は最盛期です。
広島近郊7大葉物野菜
広島市では、生産した野菜を新鮮な状態で消費者に届けられる都市近郊農業の利点を生かし、鮮度が大切な葉物野菜の生産が盛んです。その中でも代表的な7種類の葉物野菜(こまつな、サラダみずな、しゅんぎく、ほうれんそう、パセリ、青ねぎ、広島菜)を「広島近郊7大葉物野菜」と名づけ、おいしさや食べ方を積極的にPRしています。
こまつな

こまつなは、カルシウムや鉄分、βカロテン、ビタミンCなどを豊富に含む緑黄色野菜です。広島市内で生産量第1位の野菜で、市場に出回る市内産野菜の約6割を占めています。こまつなはアクが少ないため、調理が簡単なことも特長です。
おひたしや和え物のほか、生のままサラダとしても食べられます。また、こまつなに豊富に含まれるβカロテンは脂溶性の栄養素であるため、油と一緒に取ると吸収率がアップします。そのため、炒め物もとして調理するのもすすめです。クセが少ないため和食・洋食・中華など、さまざまな料理に使えます。
サラダみずな
水菜は京都原産の野菜で細長い葉とギザギザした葉先が特長です。βカロテンやカルシウムを豊富に含む緑黄色野菜です。水菜は鍋物やおひたしなどに向いていますが、広島市では柔らかくて生で食べやすい「サラダみずな」が通年出荷されています。シャキシャキした食感と鮮やかな緑色が特長です。サラダにして食べるのが最適ですが、鍋料理やチヂミに入れるのもおすすめです。
しゅんぎく

しゅんぎくは鍋物や和え物に使われる香り高い葉物野菜で、βカロテンやビタミンC、ビタミンK、カルシウムなどを豊富に含んでいます。主に11月〜3月頃出荷されています。
しゅんぎくは大葉種・中葉種・小葉種に分類されますが、広島市で主に栽培されているのは、葉の切れ込みが浅くて肉厚な大葉種の「おたふく春菊」という品種です。葉が大きくて丸く、しゅんぎく独特の苦みが少ないのが特長です。柔らかいため、新鮮なものは生でも食べられます。
ほうれんそう
ほうれんそうは、ビタミンAやC、カリウム、鉄分などの栄養素を豊富に含む緑黄色野菜です。広島市内では、11月から5月にかけて出荷されます。冬の寒さが厳しくなる季節は葉に甘味が増しておいしくなり、和え物やおひたし、バター炒め、ポタージュスープなど、さまざまな料理で楽しめます。
パセリ
広島市安佐南区祇園地区では、昭和25年頃からパセリ栽培が始まりました。伝統野菜「祇園パセリ」は葉が細かく縮れていて食感は柔らかく、苦みが少ないのが特長です。料理に彩りとして添えるだけでなく、食べてもおいしいパセリです。
青ねぎ
味が濃くて香りが強い青ねぎは薬味として使われますが、火を通すと甘くなるので炒め物や鍋物、お好み焼きにも最適です。広島市西区観音地区では「観音ねぎ」と呼ばれるねぎが100年以上前から作られています。京都の九条ネギがルーツで、京都から種を持ち帰り、観音地区の土壌をもとに改良を重ねて作られたといわれています。
広島菜
広島の伝統野菜「広島菜」は、アブラナ科の野菜で白菜の一種です。葉は濃い緑色で、幅が広く肉厚なことが特長です。広島菜のルーツには諸説ありますが、1597年頃に観音村(現在の広島市西区)の住人が京都からミブナに似た種子を持ち帰り、その後改良されたという説や、明治時代に川内村(現在の広島市安佐南区)の木原佐市氏が、京都から持ち帰った種を在来種と交配改良したという説などがあります。
広島菜は主に11月〜2月頃の寒い時期に出荷され、ほとんどは広島菜漬けに加工されます。広島菜漬けは繊維が少なくて歯切れがよく、特有の香りやピリッとした風味が特長です。野沢菜漬け、高菜漬けと並び、日本三大菜漬けに数えられます。ごはんと一緒に食べたり、チャーハンやパスタの具材にしたりするのがおすすめです。
なお、近年は種まきから1ヵ月〜1ヵ月半の若いうちに収穫した「ミニ広島菜」も出回っています。大きさは20㎝程度なので広島菜としては小ぶりですが、食感が柔らかいため鍋物や炒め物などにおすすめです。苦みやえぐみが少ないため、生でも食べられます。
広島県の伝統野菜

広島県では、伝統野菜を積極的に継承しています。広島県の伝統野菜の中からいくつかご紹介します。
観音ねぎ
観音ねぎは、広島市西区観音地区で栽培されています。一般的なねぎより白い部分が多く、香りや風味があり、柔らかくて食べやすいことが特長です。味が濃くて香りが強いため薬味におすすめですが、火を通すと甘くなるので炒め物や鍋物、お好み焼きにもぴったりです。
祇園パセリ
広島市安佐南区祇園地区で栽培される祇園パセリは、葉がやわらかく縮みが細かいことが特長です。パセリといえば、一般的には料理に添えられる脇役ですが、広島のパセリは苦みが少なく、料理の主役になる“食べる”パセリです。料理の飾りやスープに入れるだけでなく、春巻きや餃子の具材にしたり、スムージーにしたりして楽しめます。
於多福春菊(おたふくしゅんぎく)
於多福春菊とは、広島市安佐南区・安佐北区で作られている大葉種のしゅんぎくです。葉が大きくて丸いことが特長です。和え物や鍋物で食べるのがおすすめですが、しゅんぎく独特の苦みが少なく柔らかいため、サラダで食べられます。
矢賀ちしゃ
矢賀ちしゃは、広島市東区矢賀地区で生産されています。サニーレタスより葉先が赤くて細かい縮れが多く、味はほろ苦いのが特長です。一時期栽培されなくなっていましたが、2000年頃に矢賀の農家の飯田森一さんが保管していた種を使って栽培が再開されました。
小河原おくら
小河原おくらとは、広島市安佐北区小河原の農家が自家採種で生産し続けているオクラです。一般的なオクラは5角形ですが、小河原おくらは切り口が8〜9角形になり、実が大きく肉厚で、柔らかく粘りが強いのが特長です。産毛が少ないため塩ずりの必要がなく、生でも食べられます。
広甘藍(ひろかんらん)
広甘藍とは、呉市広町で明治末期から大正初期にかけて作られていたキャベツです。1965年頃にはほとんど栽培されなくなりましたが、2010年に広カンラン生産組合が設立され、復活の取り組みが始まりました。葉がやわらかく甘味があるのが特長で、呉市広町や郷原町で生産されています。
家庭菜園を手軽に楽しめる肥料のご紹介
野菜を育てる喜びや、収穫したての新鮮な野菜を味わえるのが魅力の家庭菜園。初心者の方は肥料のやり方が難しいと感じるかもしれませんが、そのような方におすすめなのが追肥不要のフマキラー「カダン感動肥料 野菜用」です。
この肥料は、植え付けや種まきの際に一度土に混ぜるだけで、約180日間効果が持続します。即効性と遅効性の肥料をバランスよくブレンドしているため、生育段階に応じて必要な肥料をしっかり供給し、野菜が大きくたくさん実ります。収穫まで追肥の必要がないため、家庭菜園初心者の方でも失敗しにくいことが特長です。
また、土壌を健やかに保つRC100(放線菌入たい肥)を配合しているため、土壌環境を改善して野菜が育ちやすい環境を作ります。家庭菜園でおいしい野菜を作りたい方は、追肥不要で野菜がおいしく大きく育つフマキラー「カダン感動肥料 野菜用」をぜひお試しください。
まとめ
自然が豊富な広島県ではさまざまな種類の野菜が生産されています。特に「わけぎ」や「くわい」は日本有数の産地です。また、広島市は産地と消費者の距離が近いため、鮮度が大切な葉物野菜の生産が盛んです。伝統野菜も積極的に継承され、生産者によって丁寧に作られています。
広島県を訪れたときは、飲食店やJA広島の直売所などで、広島の野菜の魅力をぜひ堪能してみてください。








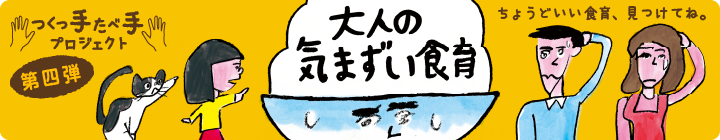
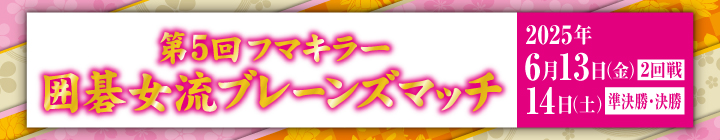

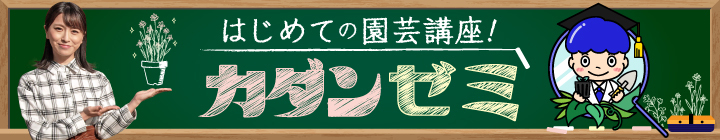
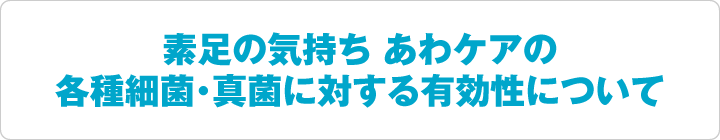
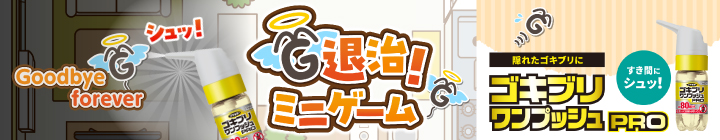
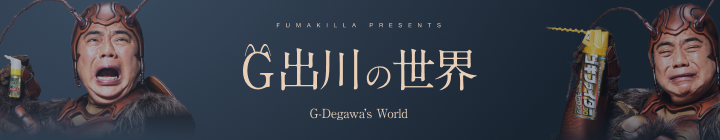






















 @ForyourLIFE_t を見る
@ForyourLIFE_t を見る



